- 専門基礎分野
- 基礎看護学
- 教育方法
- 教育評価
- ICT
コンピテンシー基盤型教育をめざして【ICTを活用した、臨床判断能力を測定する問題作成】
第0回 企画の意図と連載の方向性について
-
 動画
動画
-
 資料あり
資料あり
-
 レクチャー
レクチャー
- #臨床判断
- #ICT
- #NCLEX
- #教材
- 2023/11/02 掲載
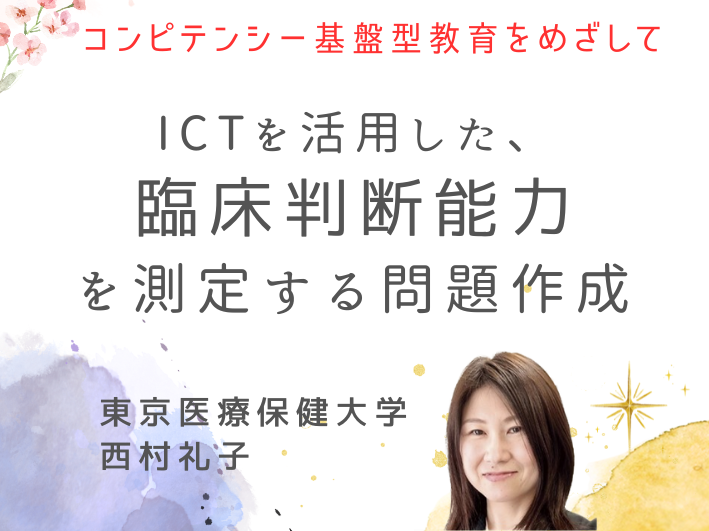
医療保健学部看護学科
【企画意図】臨床判断能力の評価に向けて
2022年、日本の看護基礎教育において、第5次指定規則改正により「臨床判断能力」の文言が追加されました。
各教育機関では、それぞれのDP(ディプロマポリシー)に基づき、臨床判断能力をカリキュラムに組み込み、検討を始めました。
全国の先生方も、それぞれの施設で工夫されながら実践されていることと思います。
それでは、カリキュラムに組み込んだ「臨床判断能力の基礎的能力」が身についたかどうか、在学中や卒業時に何が実践できるようになったかどうか、日本の看護教育では、どの段階・どの程度・何で測定・評価すればよいのでしょうか。
一方、米国でも、2023年に改訂されたNCLEX-RN®(米国の看護師資格試験)において、臨床判断能力の測定が看護師資格試験に組み込まれました。
この導入にあたって、米国では、現行の看護実践をもとに、「安全効果的に看護実践を行うためにはどのような知識・スキル・態度が必要か?」「NCLEX-RNは正しい内容を測定しているか?」という問いから、臨床判断の構成要素の文献レビューと戦略的実践分析を行い、看護実践に必要な認知理論を特定するプロセスを解明し、項目開発につなげました。
NCLEX-RNのテストプランの構造は、Client Needs・統合されたプロセス・臨床判断から成り立ち、臨床判断では、批判的思考と意思決定の観察成果と定義し、手がかりの認識、手がかりの分析、仮説の優先順位付け、解決策の作成、行動の実行、成果の評価が含まれる複数のステップからなる反復プロセスとしています。
このようにNCLEX-RN® において、CAT(computerized adaptive test)注1の機能を活用することで、看護の安全で効果的な実践に不可欠な知識、技能、能力の入職レベルをテストするように設計されました1)。
日本では、実際に臨床判断の授業・演習・科目を実践した先生方からは、学生の臨床判断が身についたか、どのように評価したらよいか、何を改善したらよいかわからないなどの声もよく聞きます。
私自身も、臨床判断能力の育成をめざした学修において、学生が学んだことを教職員と学生が共通認識を持ったうえでより実践能力の向上を目指すためには、学修した内容や到達を評価したうえで改善を目指すことが必要かと考えました。
・看護基礎教育で育成すべき臨床判断の基礎的能力とは何か
・臨床判断能力向上のために教育・授業デザインされた教育実践から生み出される教育成果とは何か
・看護学生が獲得する学修成果と看護実践で還元される看護成果とは何か
これらの問いに対する探求と検証から、看護教育の質を検討する機会が必要ではないかと考えます。
【連載の方向性】具体的な問題作成と、お伝えしたいこと
本シリーズでは、初学者である学生の(アセスメントにおける臨床推論である)徹底的検討法注2や仮説演繹法注3に合わせて、アセスメントの段階や順序性に基づきQuestion(発問や問題)を作成、ご紹介します。
具体的には、めざすコンピテンシーとアセスメントの段階とアウトカム、測定するための「問題」「発問」となる授業でのテスト、課題、アクティブラーニングでの発問、シミュレーションでのディブリーフィングでの発問やパフォーマンス項目を、パフォーマンスレベル(評価基準・評価規準項目)や到達度(マイルストーン)とともに説明します。
また、これらを実現するICTの活用(教育DX)として、音声・動画・画像・チャット・投票・コメント・CBT注4等の機能、ならびに実施時の教育者・学習者・組織の学習環境についてもご説明しながら、具体的な活用例をご紹介します。
この連載を通じて、学生のレディネスに合わせた臨床判断能力(の一部のアウトカム)を測定するQuestionの教育への組み込み方、活用方法を各教育機関で検討する一助となれば幸いです。
第1回以降では、実際の問題を紹介していきます!
ぜひご期待ください。
【注釈】
〇注1:CAT(computerized adaptive test)
コンピュータ適応型テストのことで、動的、短時間、高精度で受験者特性の測定・推定を行う方法。コンピュータには、あらかじめ目的にあわせた難易度(困難度)・識別力が推定された問題項目がプールされている。項目応答理論(IRT)によって、受験者が問題に回答するたびに、問題項目の難易度とそれまでの回答に基づいて、その能力を推定しながら、次の出題が決まっていく。受験者ごとに異なる問題を解くことになるが、同時に、能力推定値(得点の信頼)性が保証されている特徴を持つ
主に問診や身体診察に関して、網羅的に情報収集を?進め、その後で診断に関する議論を煮詰めていくような診断プロセス
病歴聴取の比較的早期にいくつかの診断仮説を思い浮かべ、それに基づいてさらなる情報収集をして診断を下すというプロセスなど
〇注4:CBT(Computer Based Testing)
コンピュータを活用した試験方法。CBTの機能により、画像・音声・動画の活用による問題、順次問題や関連問題などの、知識の統合的理解や臨床推論など、臨床に即した実践能力を問う問題が作成可能という特徴を持つ。
【文献】
1)2023 NCLEX® Examination Candidate Bulletin:2023_NCLEX_Candidate_Bulletin.pdf 2023.8.23accessed

