- 看護師
- 5年一貫
- カリキュラム
- 教育機関
- 分野
- カリキュラム
5年一貫校 新教育課程における 教育実践の取り組み カリキュラム編成から授業展開まで
浜松修学舎中学校・高等学校
- 2024/09/18 掲載
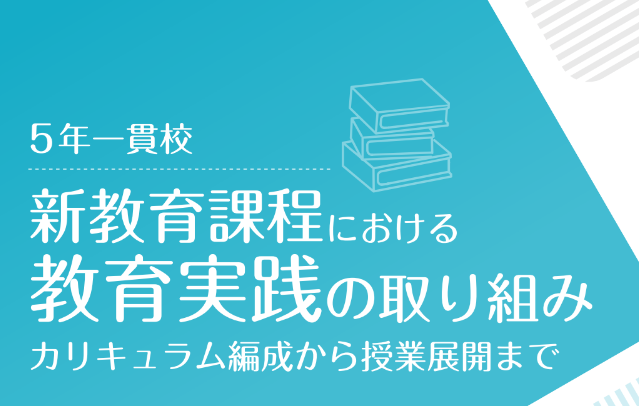
新教育課程がスタートして 2 年。改めて各校の取り組みについて伺ってみました。
各校の教育理念や教育実践の工夫を感じ取っていただけたら幸いです。
浜松修学舎中学校・高等学校

人間性も専門的な知識・技術も兼ね備えた看護師を育てたい
看護科・看護専攻科科長
日本高等学校看護教育研究所代表
大橋泰久先生に聞く
5 年一貫教育の成り立ちと背景
―― 大橋先生は 5 年一貫教育が制度として立ち上がる際の文部科学省にいらして,その後は 5 年一貫教育校の教員をされながら,全国看護高等学校長協会の活動にも役割を担われてきました。
まず,5 年一貫教育の歴史的な背景から聞かせていただけますか。
大橋先生 衛生看護科で准看護師教育を行っていた頃に,准看護師教育問題について国を挙げて改善していく議論の流れがありました。
文部省(当時)にも「高等学校における看護教育の充実・振興に関する調査研究会議」が設置され,衛生看護科の在り方について検討されましたが,これからは准看護師教育から看護師教育に移行することが望ましいという結論が出されました。
当時私は看護科教員だったのですが,文部省の会議にも委員としてかかわってきましたので,平成 13 年から文部科学省に教科調査官として呼ばれ,平成 14 年度から始まる 5 年一貫教育制度の立ち上げにかかわることになりました。
5 年一貫教育制度の目的は准看護師養成ではなく,高校でそれまで行ってきた衛生看護科での准看護師教育に加え,2 年間の専攻科の教育をプラスして,5 年間で准看護師を経ずに看護師の資格をとる教育をしていくことです。
言ってみれば,まさに教育内容の改善につながったわけですよね。ですから,現場にいたわれわれとしては,いったん准看護師のための完結教育を行って,それからさらに 2 年間の看護師教育をやるよりも,最初から 5 年間で看護師を目指したほうが効率よい教育ができると思いました。
そして,「将来,人のために役に立ちたい」という純粋な気持ちから看護師になりたいという思いで中学校から上がってくる生徒が多かったので,その希望・夢を叶えられるような,よい制度にしていこうと思いました。
教育の改善ができる本当によい機会だったと思っています。
准看護師教育と看護師 2 年教育の中ではやはり重複するところがかなりありましたので,文部科学省で検討した際には,それを学習指導要領の中で整理して,5 年間で効率よく看護師資格がとれるように法整備をしていくのが目標でした。
生徒たちの人間性も大事にしながら,最初から専門的な知識・技術が身につくような形でカリキュラムを改善していったわけです。
ところが,法律改正にあたり,教育現場がどれくらい理解して対応できるかという課題がありました。
地域によっては,その学校周辺では准看護師のニーズが高いといった地域ももちろんありました。
5 年一貫校になるよりも,むしろ衛生看護科で准看護師教育を続けていきたいという学校もありましたので,全国的に調整をしながら進める必要がありました。
また県立高校もかなりありましたので,その場合,さらに専攻科を設置して 5 年一貫教育にしなくてはいけないという事情があり,財政的に可能かどうかという検討も含めました。
当時 165 校ぐらいの衛生看護科がありましたが,5 年一貫教育に移行したのは 65 校ほどでした。
当初の見込みよりも学校数は減りましたが,きちっとした教育体系の中で学習指導要領に基づいた看護師教育が行えるという意味では,本当に少数精鋭の教育ができるようになったと感じています。
―― 5 年一貫教育がスタートした当時,教育現場の負担感はなかったのでしょうか。
大橋先生 私の現場経験では,生徒たちについては求めれば求めたところまで努力してくれるものだと感じています。
逆に言うと,教員側が生徒に求める目標の設定を低くしてしまうと,生徒はそこまでしか伸びません。
ちなみに,人間教育については,准看護師養成課程でも看護師養成課程でも,高校の 3 年間における教育内容はあまり変わりませんでした。
ただ,准看護師養成課程に比べて看護師養成課程のほうが専門性はかなり高くなりますから,教育現場では二の足を踏んだところはあるかもしれないですね。
私の経験からすると,准看護師養成にとどまっていた教育を,さらに専攻科
の教育に結びつけるような深い教育にしていくことで,目標さえ提示すれば生徒は結構応えてくれます。
したがって現場には,「准看護師教育から看護師教育に,場を変えてやっていきましょう」とガイダンスしていきました。
カリキュラムも当然,准看護師教育と看護師教育に対応した内容も読める形で学習指導要領を改訂していきましたので,自信をもってやっていただけたらと思ったのです。ですから,真摯に向き合って教育を変えてきた学校では,それなりに変化や手応えがあったのではと思います。
―― それまでの衛生看護科で行っていた准看護師養成の教育内容から看護師養成課程の一貫であるという意識は,当時の教育現場でなかなか浸透しなかったのではないでしょうか。
大橋先生 そうですね。文科省の教科調査官のあと神村学園の教育に携わりましたが,当時の鹿児島県の研究会や九州地区の校長会・研修会での話をお聞きすると,九州地区のほとんどの 5 年一貫校が,「今までどおりに高校 3 年間は准看護師養成課程用の教科書を使って,専攻科で看護師養成課程用の教科書に切り替える」というカリキュラムを敷いていました。
文部科学省時代には 5 年一貫教育の目的を示して「ここで変える」「指導者がここまで求めれば大丈夫」と説明したつもりでしたが,十分に浸透しきれなかったかもしれません。
―― 恐らく九州地区だけでなく,全国的に同様な状態だったのではないでしょうか。
大橋先生 そうですね。しかし,最近,使っている教科書の調査をしましたら,かなり改善されてきていることがわかりました。
ただ地域差もあります。最初の高校 3 年間で准看護師養成課程用の教科書を使っている学校はまだ半数ほどありますが,九州地区では以前よりもだいぶ変わってきています。
これから分析するところですが,電子教科書が普及したことで,電子教科書で看護師養成課程用の教科書を高校 1 年生のときから使える環境が整ってきたことも少し影響しているのかなと思います。
確かに,准看護師養成課程用の教科書のほうがわかりやすい文章表現が多いので,授業の中で教員が准看護師養成課程用の教科書を参考にしながら授業を組み立てていくことで看護師養成課程用の教科書の難しさをカバーできる,ということが背景にあります。
神村学園のカリキュラム改善について,私が最初に言ったのは「准看護師養成課程用の教科書を使うのはやめましょう。
最初から看護師養成課程用の教科書を使って 5 年間の教育ができるようなカリキュラムに変えていきましょう」ということでした。
と同時に,既に数社から電子教科書が出ていましたので,「この際,教科書の電子化も図っていきましょう」ということでした。鹿児島県内では同様に鳳凰高等学校なども同じ方向で進んでいましたので,よい方向に向かってきていると思いました。
たとえば准看護師養成課程用の教科書プラス看護師養成課程用の教科書を使った学校と,5 年間とおして看護師養成課程用の教科書を使った学校の国家試験合格率などを分析していく予定です。
全国看護高等学校長協会の概況調査の結果として,各学校が本当によい看護師教育を行っていくためにはどんな工夫が必要なのかということを,お返しできればと思っています。
―― それは,日本高等学校看護教育研究所での調査活動になりますか。
大橋先生 そうです。今まで全国看護高等学校長協会で全国の概況調査を行って項目ごとの集計までして,各学校にお返ししているのですけれども,クロス集計を行うことにより,どんなカリキュラムで,どんな教科書を使って,どんな工夫をした学校が,国家試験の合格率が高い・低いとか。あるいは進路についての傾向で,5 年間の教育が終わってすぐ現場に就職する生徒と,それからさらにキャリアアップのために大学に進学する生徒という違いもありますので,そういう違いはどこからくるのか,そんなことが集計できたらなと思っています。
なかなか難しい調査ですけどね。ただ教科書については教育と密接にリンクしていますので,かなりその傾向がはっきりとわかりますね。
5 年一貫校で准看護師養成課程用の教科書を使っている学校もありますが,ただ私とすれば,確かに看護師養成課程用の教科書は難しいけれども,それを高校 1 年生からしっかりとわかりやすいように教えていく工夫が教員の先生方にはできると思っていますので,そういう努力をしてもらいたいなと思っています。
―― 看護科(衛生看護科)の教員の先生方は,担任をもったり,クラブ活動をもったりと,看護師教育を合わせてやるという負担感はないのですか。
大橋先生 もちろん多いですよ。本校でも教員採用の際には,皆さん看護師の資格があって,教育にも興味のある方に来てもらっていますが,自分たちが受けてきた看護教育と高等学校での看護教育との違いに,やは
り戸惑いはありますよね。何より一番大切にしなくてはいけないのが人間教育のところ。やっぱり,高校を卒業した生徒に対する人間教育と,中学から上がってきて一番多感な時期である 15 歳から 20 歳の生徒に行う人間教育はおのずと違ってきます。高等学校では本当に打てば響くような教育ができるぶん,教員の負担感はかなりあります。
―― 専攻科から看護科に異動される先生は大変なようですね。
大橋先生 そうですね。そこで,看護科プラス専攻科のように,看護科の教員,専攻科の教員と組織が別々になっているところが多かったので,「5 年一貫教育の学科として,教員も順番に看護科と専攻科を行き来することができるような組織づくりをしていきましょう」と言いました。
―― 大橋先生は,5 年一貫教育の制度ができたときから,そういった組織づくりについて提案していたのですね。
大橋先生 そうなんです。文部科学省で 5 年一貫教育の制度を全国の学校にガイダンスしていたときに,やはり組織づくりが大切だと言ってきました。
ただ,専攻科が既にあった学校では,もともと建物が別であったり,職員室が別であったりしますので,物理的な距離はあります。
神村学園や本校もそうなのですが,看護の 5 年一貫課程ということで,教員は 1 つの職員室に全員います。
当初,神村学園も組織は別々だったのですが,今は同じ職員室で 1 つの組織です。専攻科の教員が看護科のほうで教育にあたることも大事だということで,年度に応じて行ったり来たりをします。物理的な距離がない学校については,それもかなり進んできています。
―― 最初に制度をつくったときの明確なコンセプトが,約 20 年のプロセスを経て少しずつ形になってきているという感じですね。
大橋先生 ええ。平成 19 年から 5 年一貫校の卒業生が出るようになりました。実習病院の関係で静岡県内を回ったりすると,5 年一貫校の卒業生ですと言う看護師が,ちらほらといるんですよ。そういう人たちがほかの専門学校や大学を卒業した看護師と何か違いがあるのかというと,そんなことはありません。これは手前みそになるかもしれませんが,むしろ 5 年一貫教育で育った看護師のほうが患者さんの傍らで一生懸命で,スタッフナースとして親身に働いてくれる人が多いという評判を聞きます。もちろん,お世辞で言ってくれるのかもしれないですけどね。われわれはそれを糧に,5 年一貫教育の特性として 15 歳から生徒を育てていますので,患者さんのことを最初に考えて行動できるような看護師を育てたいと思っています。神村学園のときも本校でも,「看護師の一人称は,I じゃなくて You だ」という合言葉でやっていきましょうと言って教育しています。
浜松修学舎高等学校の教育の特色について
―― 浜松修学舎の教育方針についてうかがえますか。
大橋先生 先ほども言いましたように,5 年一貫教育の最初の 3 年間は高校教育にあたり,子供から大人になっていく中で人間性を育てることが非常に大切なのですが,あくまでも 5 年間の看護師教育の最初であるので,人間教育を重視しながら,専門性の基礎をしっかりと育てることを大事にしています。
豊かな人間性を育成することはもちろん,看護師として必要な,職業に関する使命感,責任,あるいは協力していける力を育てるという目標があります。
ただ,5 年一貫教育の看護師教育とすれば,一番の基礎になる「基礎医学系科目」はしっかりと身につけなくてはいけません。「基礎医学系科目」と,「基礎看護学」の「看護とは」というところをまず理解してもらうことを大切にしながら教えています。
本校が一番大切にしているのは,「将来の自分の姿」をしっかり描くということです。人間教育や専門教育を受ける中で,将来 10 年後・20 年後に自分がどういう形で社会に看護師として参加しているかをしっかりと可視化して,それを目標に段階を踏んで自分に足りない力を身につけていく。
ですから高校 1 年生のときに,看護科の主任を中心にして,自分の将来の姿をしっかりと描いていこうという働きかけをしています。
―― 生徒に具体的な将来像を描かせるのですか。
大橋先生 これは神村学園から継承したのですが,「対話ノート」というものがあります。式典などで理事長・校長の話を聞いたり,外来者の講演を聞いたりする機会がありますよね。
通常は,そういう行事や講演会で聞く話は恐らく聞きっぱなしで,早ければその日のうちに内容を忘れてしまうのではないかと思いますが,
神村学園ではメモを取って,その内容を要約して,それに対する自分の考えや思いを書かせる記録ノートをつけさせていたのです。それは本当に大切なことだと思いました。記録ノートがあると,たとえば入学のときに校長から聞いた話から,自分は将来こういう看護師になりたいなと思ったことが記録として残るわけですね。
そのメモをことあるごとに見て,自分がそのときに思ったことをきちんと受け止める。
そうしないと,高校生時代ですから,「本当に看護師になりたい」「困っている患者さんに頼りにされたい」と思って入学しても,生活していく中で勉強が大変だったり,あるいは恋愛もあったり,予想もしていなかった方向へ流れてしまうこともあります。
そんなときに初心に帰って記録ノートを開き,色々な人から聞いた話,あるいは自分が思ったことを見返してみると,ぶれない将来の姿が描けていけます。
生徒は必ず持っているんですよ。
始業式や入学式,講演会などのときには必ずノートを持ってきて,聞いたらすぐに書かせます。
―― 生徒同士の交流はどうでしょうか。
大橋先生 本校にはまだ 3 年生までしかいないのですが,多くの 5 年一貫校では,5 年の年齢の違いを活かして,他学年との交流の機会をもつことをずいぶんやっています。
―― もともと 5 年一貫教育は,そういうことも念頭においていたのですか。
大橋先生 いや,当初はそこまで考えていなかったのですが,それまでの准看護師養成時代も高校 3 年間の中で 1 年生~3 年生での交流はやっていました。
ところが 5 年一貫教育となると 15 歳と 20 歳という,まさに大人と子供ですから,その交流によって 1 年生も「将来の姿」が可視化できる。
5年生も 1 年生を見て自分たちの成長した姿を確認できると思いますので,今後やっていきたいと思っています。
―― 1 クラスは 40 名ぐらいですか。
大橋先生 70 人定員で,35 名のクラスが 2 クラスです。
1 年ごとにクラス替えがありますが,そこもよいところです。
中学校から上がってくる生徒たちの意識は本当に純粋なんですよ。
自分の経験,あるいは小説,漫画やドラマの影響もあるかもしれませんが,とにかくけがや病気で苦しんで困っている人のために何とか役立ちたいという純粋な気持ちで入学してきます。
ほとんどの生徒が同じ目標をもち,同じ気持ちでいるので,そういった集団の共通の意識がありますね。
そういった純粋な生徒の気持ちを大事にしながら教育しています。
学習指導要領改訂に沿ったカリキュラムの工夫について
―― 学習指導要領の改訂があった中で意識した点はありますか。
大橋先生 5 年一貫教育ということで,なるべく基礎科目を高校 3 年間のほうにおくわけですが,本校の特徴としては,1 年生から臨地実習を入れていることがあります。なぜかといえば,先ほど言いましたように「将来の自分の姿を可視化させる」という目的のためです。
昔は看護学校を卒業したら,看護師の就業場所,活躍できる場の 98%ぐらいが臨床でしたが,今は臨床だけではなく,施設であったり,学校であったり,幼稚園だったりと色々な場所で看護師が求められています。
本校は臨床看護師を養成する学校としてではなく,看護師が専門性を踏まえて色々な場所で活躍できるように,自分がどういう場で活躍したいのかを決めて卒業ができるように,1 年生のときから病院だけでなく,介護施設,児童養護施設など,さまざまな実習場所に行かせています。
もちろん学年に応じて 1 年生は見学実習が主になります。2 年生になると病院・施設などの看護師に同行して同行実習。
そして 3 年生になると今度はそれらの場で,成人看護,老年看護や在宅看護の教育目標に応じて,部屋持ちか受け持ち制にして看護をしていきます。5 年間の色々な体験を通して,将来の自分というものがわかるようになります。
―― カリキュラム上で配慮したところはありますか。
大橋先生 学習指導要領にある「情報Ⅰ」を残しました。
通常は専門科目の「看護情報」で代替して,「情報Ⅰ」については履修しない学校が多いんですよ。
ただ「看護情報」は看護の場面での情報処理ということで,かなり専門性が高い内容になります。
一方で必履修科目になっている「情報Ⅰ」を見ると,情報のリテラシーであったり,情報モラルやセキュリティのことであったり,まさに情報の基礎なのです。
ですから,本来そこをしっかりと学んだうえで,専攻科で看護に特化した「看護情報」を学ぶほうがよいと考えて,本校では代替をせずに「情報Ⅰ」をまず学ばせることにしました。
また「普通科目」と「看護科目」との系統上のかかわりをしっかり持たせるために,看護に活かせる知識としての普通科目の配置を工夫しています。数学であれば,看護師としてどういう数学的な力が必要なのかを考えて配置します。
「物理」「化学」「生物」も同様です。
高等学校で看護教育を行うことに関して言うと,高等学校の基礎科目の部分は自由になっていますので,そこを看護教育に関連づけていくことが必要なのかなと思
いますね。
5 年一貫教育の教科書・参考書について
―― 教科書や参考書はどのようにされていますか。
大橋先生 本校では最初から看護師養成課程用の教科書を採用する予定でいたのと,iPad で教科書の電子化を図ることを計画していましたので,電子教科書を発行している出版社からのプレゼンを受けて,最終的に「系統看護学講座」の電子教科書に決定しました。
教員の先生方は「系統看護学講座」だけではなく,高校生に内容をいかに噛み砕いて教えるかということが大事になりますので,他社の教科書・参考書,雑誌の中から
も非常に有効で価値があるものは参照しています。
生徒・学生向けの雑誌は本当にわかりやすく書いてありますね。
当面は電子教科書でいく予定です。最初は教員に使いこなせるかどうか心配しました。むしろ生徒が上手に使ってくれますね。われわれより使いこなしています。
―― 副教材,教具はどうでしょうか。
大橋先生 今は電子教科書,コンピュータ上で再現されるような図表のほうがよいですね。
あとはシミュレーターをたくさん用意しています。
やはり生徒が患者さんに直接手を触れるような実習はあまりないですから,学校の中でシミュレーターを使って技術についてしっかりと教育したうえで,実習ではそれを確かめる形にしたほうがよいだろうと考えています。
シミュレーターは,「Physiko」が 2 台,「さくら」も 2 台あります。それから「ふりかえ朗」「シナリオ」「ラング」など,結構あります。
部分的な実技が演習できるものでは,気管挿管であったり,採血だったり,注射であったり。
これまでのような,学校の中で一生懸命に技術を覚えて,実際に実習に行ってみるとできなくて怒られて,その結果,ビクビクしながら実習に行くようになる,という学び方ではなくて,どんな新しいことが発見できるのだろう,自分が学んだことは確かにそうだったんだろうかと確かめられるような,わくわくドキドキした,楽しい実習にしたいと考えています。
人間性も専門的な知識・技術も兼ね備えた看護師を育てたい
―― 最後に,大橋先生が 5 年一貫教育の中でどういう看護師を育てたいか,そのために教員はこうあってほしいという点を聞かせいただけますか。
大橋先生 職業教育なので,専門性の知識・技術を備えることは必要なのですが,一方で現場からは人間関係を構築する能力であったり,患者さんの側に立ってものが考えられたりする人間性も強く求められます。
どちらかということではなく,人間性も専門的な知識・技術も両方備えた看護師を育てていきたいなと思います。
高校から看護教育を受けたいという思いで入学してきた生徒たちは,こちらの期待に本当によく応えてくれます。
国民から信頼される看護師になろうねと言えば,何が必要なのかをわかってくれるし,その意味で大変やりがいがあります。
―― 課題を課せば生徒がそこまで伸びるということを,教員が信じることが必要ということですね。
大橋先生 「必要なのは生徒に対して到達可能な目標を連続して提示いくことだよ」と,教員の先生方にはいつも伝えています。
あまり大きな目標をいきなり立てても,生徒は途中で挫折したり,くじけたりしますので,実際に到達可能な目標を設定して,クリアしたらまた到達可能な目標を設定する。
その連続の中で生徒が伸びていきます。
ですから教員は授業に際して必ずどういう目標をもって臨むのかを考え,生徒には,その単元でどんな力が身につくのかを提示したうえで,授業をしていきます。
それから,高等学校の校長先生は看護師免許をもっているケースがほとんどありませんので,看護師の特性を理解したうえで支援していく姿勢もとても重要だと思っています。
看護科の教員の指導方法に課題があるという指摘もありますが,看護師は何か課題があれば,それがどういう原因で起きているのか,どういうプロセスで課題になっているのかをきちんと分析・アセスメントします。
そして解決するためにはどんな対策が必要で,何をやったらよいのかを考えます。
それを実施していく中で力をつけていくプロセス自体が看護の取り組みです。
看護科の教員は皆それができる人たちです。
それを校長先生方が意識して,生徒指導や教科指導にあたるように導いていけば,学校全体で看護師の取り組みを上手に生かしていくことができると思います。
看護の先生方って,課題解決能力にたけていますからね。


