- 看護師
- 基礎分野
- 基礎看護学
- 教育の基盤
- 教育論
- 教育方法
理論と実践をつなぐ事例研究 看護理論活用ガイド
第2回 ローズマリー・リゾ・パースィの看護理論
-
 レクチャー
レクチャー
- #看護理論
- #パースィ
- #事例研究
- 2025/05/13 掲載
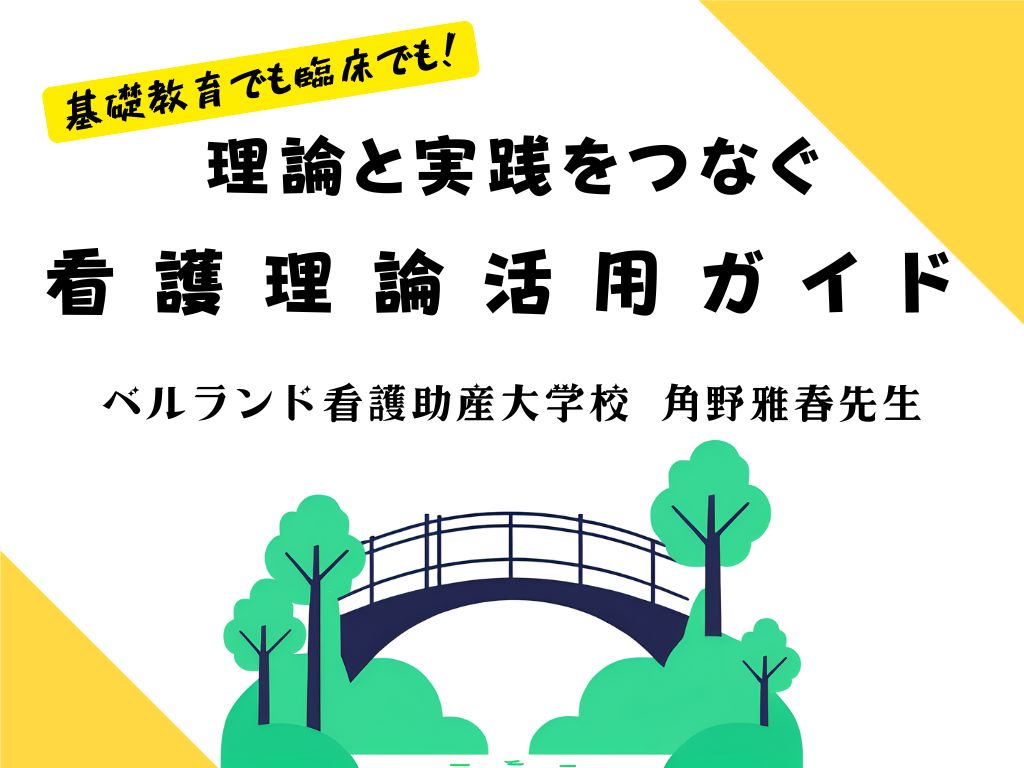
|
「看護学生や(現場の看護師)が、 実践と看護理論を結びつけて実践を考えるために、看護教員ができること」 本連載では、ベルランド看護助産大学校で教員として勤務されながら、臨床看護学の研究にも携わられる角野雅春先生が、毎回1つの看護理論と共に、その看護理論を用いてどのように学生や看護師の実践を共に振り返ったのか、理論の説明と看護実践の2本柱で紹介いただきます。 |

はじめに
パースィは“健康を変化させる方法”について、「人は価値の優先順位が変化した時に、看護者と真に共に在ることの中で健康パターンを変化させる」と述べ、その方法のひとつに、「創造的にイメージすること」を挙げています1)。
また、”イメージする”とは、「ある変化が既に起こっている中でシナリオを構成し、それを試みようとしてその変化に慣れ、期待するように思い描くことによって、変化がどのようなものかを知ること」と示しています。
例えば、人は「転職したらどのようになるのか、居住形態をを変えたら、あるいは動けなかった人がまっすぐ立って歩くとしたらどのようになるか」というようなシナリオの構成をするでしょう1)。
今回、取り上げる看護学生は次のようなシナリオを構成しました。
「活動性の低下している患者が、好きなイラストを見ようとしたらどうなるのか。今よりも、少しは座っていようとするのだろうか」
今回は、地域包括ケア病棟に入院する患者を受け持った看護学生Sさんの看護実践を「パースィの看護理論」を用いて振り返り、Sさんが「看護とは何か」について思いめぐらせた看護実習の経過と、Sさんと私の対話の過程をお伝えできればと思います。
Sさんの看護実践を聞き、共に考える
看護学生のSさんは実習期間中、「私は何をしているのだろうか」「これは看護なのか」という迷いの中、受け持った患者さんの看護ケアに当たっていました。
Sさんが受け持った患者さんは、肺炎による入院に伴い入院関連機能障害(HAD:Hospitalization-Associated Disability)を生じ、介護保険施設への入所、もしくは自宅への退院に向けてリハビリテーションに取り組む方でした。
入院関連機能障害とは、「直接的には運動障害をきたさない疾患(肺炎、心不全、悪性腫瘍など)のために入院した時に発症する、安静臥床(不動)を原因とした身体機能低下、認知・精神機能低下」と定義されます。
受け持ち当初の対象の様子
Sさんは受け持ち当初、対象が食事や排泄時、リハビリテーションの実施時の限られた時間のみ離床しており、日中のほとんどの時間をベッドで臥床して過ごしている様を目の当たりにし、対象の臥床傾向が続くと入院関連機能障害を断ち切ることができないと考え、少しでも離床を促すべく様々な療養生活の間に余暇活動を取り入れること検討し実施したのですが、うまくいかなかったと話します。
例えば、まずSさんは対象が少しでも病床で臥床している時間を減らすことを目的に、談話室でボードゲーム(オセロ)をすることを提案しました。対象は学生の提案を受け入れ、談話室までともに歩行器を用いて移動しボードゲームを行っていましたが、対象は黙々とボードゲームを行うのみで、3日目には「もうボードゲームはしたくない、部屋にいたい」と拒まれてしまいました。
次に、Sさんは対象が唯一好きなものとして聞いていたマリーゴールドの寄せ植えに着想し、病床でも座位でいる時間を増やせること、病室で車いすに移乗したりできることで不動を減らそうと考え、マリーゴールドの塗り絵を提案しましたが、対象から「塗り絵には興味がない」と関心を示されることがなく、実施にいたることができなかったと話します。
それから、Sさんは日々、バイタルサインの測定や食事、清潔など療養支援などを実施し、7日ほどが経過しました。
そんな中、「私は何をしているのだろうか」と思い、悩んでいたと話してくれました。
Sさんの看護を振り返るきっかけとなった気づき
そこで、Sさんが対象と共に過ごした10日ほどを一緒に振り返ると、Sさんは受け持ち当初から、対象のサイドテーブルに朝食の牛乳パックの空き箱が“綺麗に2、3個並んでいる”ことが気がかりであったと話してくれました。
そして、この牛乳パックについて対象に尋ねと、対象は「この牛乳パックの絵柄が好きなの、可愛いから」「ずっと見ていられるの」と、笑みを浮かべながら話されたといいます。
Sさんはこの場面を振り返るまでは、対象がほとんどの時間を病床で臥床していると思い込んでいたと話します。そこで、私は学生と対象の「牛乳パックを綺麗に並べ眺めている」という行為の意味について考えてみましょうと話しました。
パースィの看護理論
パースィは、「看護者」について以下のように述べています2)。
|
看護者 それぞれの個人や家族の質に関する独自の考え方を尊重し、自分の考えに合わせるようにその人たちの考え方を変えようとはしない。 |
そして、また「生活の質」について、以下のように述べます3)。
|
生活の質 人生を生きているその人、あるいはそれらの人々によってのみ表現される。なぜなら生活の質とは、その人たちの渾然として調和のとれた生成の意味を具現化したものであるからである。 |
また、高橋は、パースィの人間生成論にある、
|
その人や家族あるいはコミュニティと共にある看護師は、その状況の意味を話し合うよう導かれている。意味について話し合う中で、自分自身や家族や看護師らとともに考えや感情を共有する。 |
という説明を用いて、
「あなたのためだから・・・」「・・・すべきである」とするのではなく、患者らを尊重する中で、その人とたちの願いの「意味を照らし出していく」ことが患者中心の看護の考え方であると説明しています4)。
Sさんの看護実践とパースィの看護理論の当てはめ
Sさんは、肺炎を患い入院の間多くの時間を病床で過ごす対象が、入院生活の中で営んでいる“眺める”という行為に含まれる、対象にとって「価値ある喜び」という感情を共有しようとしていました。
そして、Sさんは対象に「サイドテーブルに並べている牛乳パックの絵柄を紙一面に貼って見られるようにしてみませんか?」とお話すると、対象は微笑み、「良いね。そうしたい」とおっしゃったようです。
Sさんが対象の元へのりとはさみを持っていくと、対象は自ら座位となり、はさみを持って牛乳パックを切り始めました。切った絵柄を画用紙に貼り、完成した時には「これ良いね」「いっぱい貼ったらもっときれいだろうね」と話し、その画用紙を手に取ってしばらく眺めていました。
Sさんもまた、対象の隣でその様子をそっと見守り、一緒に座って牛乳パックで作成した画用紙の絵を眺めたといいます。
そこで、私は、看護学生が対象の価値に目を向け、対象の“眺める”という意思を尊重し、対象の希望を理解しようと努めようとするSさんの看護について、「パースィの看護理論」を用いて考えることを提案しました。
どのような時に、パースィの看護理論が参考になるか
パースィの看護理論は人間生成論と示され、患者に対して対面的な話し合いや、静かに身を置くこと、長く居ることによって、「真に共にあること」を示す理論です。
「真に共にある」とは、看護者のあり様を指し、真に共にある看護者は、他者が人生のその時の意味に新たな光を与えることを見守ることができる、と説明されています。
そして、「真に共にある」を実現するには、「意味を照らし出す」「リズムに同調する」「超越を結集する」という3つの看護実践が示されます。
それぞれ、以下のようなことを意味すると、パースィは言います3)。
「意味を照らし出す」
現在何が起こっているのかをはっきりさせることを意味し、何であったか、何であるか、ということを明らかにすること。
「リズムに同調する」
他者のあり様や思いに看護者が寄り添うこと。
「超越を結集する」
まだ起こっていないことに対しての、現在の意味を超えていくことで、心に描いた変容の可能性を推進すること。
以上のことから、
- 対象の”ある行動”に関心を持って、理解したい
- ”ある行動”によって生まれる対象の感情に共感したい
- 対象に寄り添いながら、対象が自ら望んで行いたいと思うことを見いだしたい
といったことを学生が考える際、パースィの看護理論が参考になるかもしれません。
パースィの看護理論を用いたSさんの事例研究
それから、Sさんは対象に対して、絵を見るという行為で日常生活行動を拡大する有用性を「伝える」のではなく、対象自身が主体的に行いたいと思う行動を継続して実現するための支援ができないかと、対象の病床を訪室することとしていきました。
Sさんは、パースィの述べる「真に共にある」看護とは、学生自身が療養における活動促進の価値を対象に教えたり、それに向けて学生が「こうすべき」と、何か活動促進のためのきっかけを準備したりするのではなく、患者自身の価値を尊重し、理解した結果としての支援であると考え始めました。
Sさんは対象に工作を提案した翌日に訪室した際、対象が工作を完成させた時と同じように牛乳パックを貼った画用紙を手に取り、病床に座り、画用紙の絵を眺めている様子を見ることができたといいます。
また、Sさんが対象に「どうなさいましたか」と伺うと、「きれいじゃない?ずっと見てられる」と話す対象の笑顔を見ることができたと話します。
それからは訪室する度、対象と作成した画用紙を手に取ったり、椅子に腰を掛けたり、絵画を眺めながら談笑したりと、一緒に微笑みながら過ごす時間を共有していきました。そして、病室を後にするときに、対象から笑顔で「ありがとう」という言葉を聞いたと教えてくれました。
これらの看護学生のSさんの行動は、パースィが人間生成論で述べる、”対象の傍らに静かに身を置き、対象のリズムに同調する、つまりその人に寄り添い続けそのリズムと共に歩む看護”であったと言えるのではないでしょうか。
ややもすれば、牛乳パックを並べる、そして、牛乳パックを切って貼り、それを眺めるという行為は、この2者間でしか分かり合えないことであり、「なぜ牛乳パックを集めて切って貼っているのか」「牛乳パックの絵柄を見ることに何の価値があるのか」などは第3者からすると分かり合えない現象であるかもしれません。
また、看護学生の実習においては、”対象のテーブルに残された朝食の空の牛乳パック”という認識であったならば、環境整備という観点で廃棄していたかもしれません。
第3者から理解しがたいことでも、その2者間では価値のある現象であり、「真に共にあり続ける」ことという2者の関係でいられることが、看護者としてのあり様であると考えることはできないでしょうか。
理論を用いた事例研究で見えてきたSさんの実践の意味
パースィは、看護学の目標について、看護の対象である「その人、その家族とコミュニティの視点からの生活の質」の向上であり、「その人の生活の質を高めるように、その人とともにあることである」と述べています。
Sさんは、対象を受け持った当初、入院関連機能障害を断ち切ることを目標に、余暇活動の提案や病床からの離床をはかろうとしていました。
もちろん、学生として活動耐性低下をきたす対象への看護を考え、実践することの意味は大きいと思えます。
しかし、Sさんが対象の「特にどこか行きたいとかない。したいことも特にない」といった言葉を受け、活動意欲が低い状況と捉えて、関わりをやめていればどうなっていたでしょうか。Sさんと患者の関係の発展はなかったことでしょう。
対象の持つ価値について関心を持ち、対象が望むことについて看護を探究していく過程は、Sさんが対象の“リズムに同調していた”と考えることができます。
また、Sさんが対象の入院生活の中で営まれる行動の価値を知り、そして、「いっぱい貼ったらもっときれいだろうね」と語る対象は、これからの希望の療養生活を思い描いているといえます。
このことは、心に描いた変容の可能性を推進する、つまりパースィの看護理論でいう“超越を結集する”に当てはまるのではないでしょうか。
対象との関わりの中で、“リズムに同調する”ことや“意味を照らし出す”こと、“超越を結集する”などの過程を経て、Sさんは「これから飲み切った牛乳パックを切って貼って、この画用紙に集めていきませんか。そして、画用紙1面にある絵柄を一緒に見ませんか」と提案し、対象も笑顔で「それ、いいね」と同意されます。
その後、牛乳パックを切って貼り画用紙を眺めることは、対象とSさんの間で習慣化されていきます。
このプロセスの中で、対象が自ら望んで行いたいと思うことを看護学生は見いだし、見守っていました。
対象とSさんは“真に共にある”関係であったといえるでしょう。
そして、この看護は、対象において活動時間の増えるきっかけにもなり、当初、Sさんが考えた入院関連機能障害を断ち切る支援も同時に図れ、対象の心身共に健康な状態を促進する看護として、学び得たのではないでしょうか。
Sさんは対象の行動を捉え、その結果がもたらす意味を照らし出し、新たな価値に気づくことができました。
“真に共にある”看護により、対象は入院生活において、自ら活動したいと思える行動を見いだし、その行動から楽しみを見いだすことができたと言えます。
パースィの看護理論に基づく「看護」とは
看護者は、何もせずその対象の決めることを待つのではなく、その人や家族らが決断をするために必要な情報を十分に提供する存在であり、また、看護師自らの意見を押しつけたりするのではなく、ともに考え、悩み、寄り添い、対象が納得のいく決断ができるように援助する存在です。
先にも述べたように、パースイの看護理論によると、看護者は「その人あるいはその家族の質についての考え方を尊重し、その人たち自身のもつ考えや見解を変えようとはしない」と明記しています。
また、パースィは「真に共にあること」を次のように述べています5)。
| 対話的な話し合いや、静かに身をおくこと、長く居ることにおいて実現される看護者のあり様を意味する。 |
パースィの看護理論でいう「意味を照らし出す」「リズムに同調する」「超越を結集する」という過程を全て経てはじめて、真に共にあることにたどり着くわけではないのかもしれません。
もしかすると、本症例にみられたように、対象の朝食で出てくる牛乳パックの空き箱がきれいに2、3個並んでいたことに対して看護学生が気がかりを持った時、すでに“真に共にある”ことは始まっていたと考えられないでしょうか。
つまり、パースィも述べる
| 真に共にあることは、すでに他者と実際に一緒になる前に、準備と集中をもって存在するようになるその時々において始まっているのである5)。 |
という理論に帰着できたと考えられます。
Sさんは、「看護とは何か」の問いに対して次のように答えます。
「わたしは受け持ち当初、その人を本当の意味で知ろうとしていたといえるだろうか?その人のことをを知らずに、看護はできない」
そして、Sさんは今後、「知ろうとすること、そして、知るということが看護である」と自信を持って答えることができるでしょう。
|
[引用文献] [参考文献] ・西村ユミ, 山川みやえ(編): 現代看護理論―一人ひとりの看護理論のために. 新曜社, 2021. |

