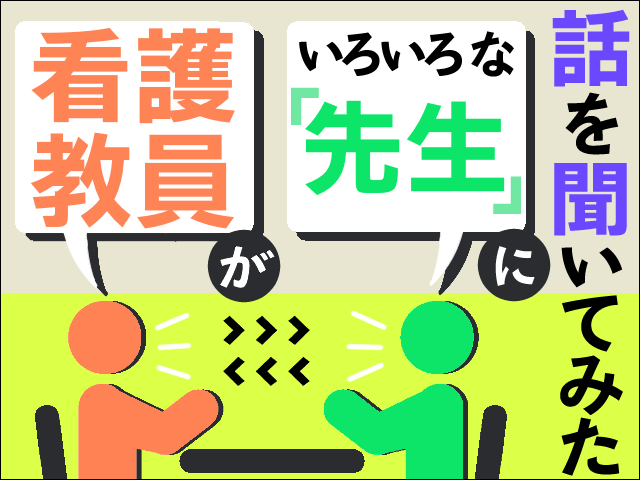- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 教育の基盤
- 教育論
- 教育方法
看護教員がいろいろな「先生」に話を聞いてみた
古賀徹先生に聞く 看護教育においてリベラルアーツを育む力と 通信による教育方法の向上
-
 インタビュー
インタビュー
- #リベラルアーツ
- #大学教育
- #オンライン教育
- #看護教員
- 2025/03/25 掲載
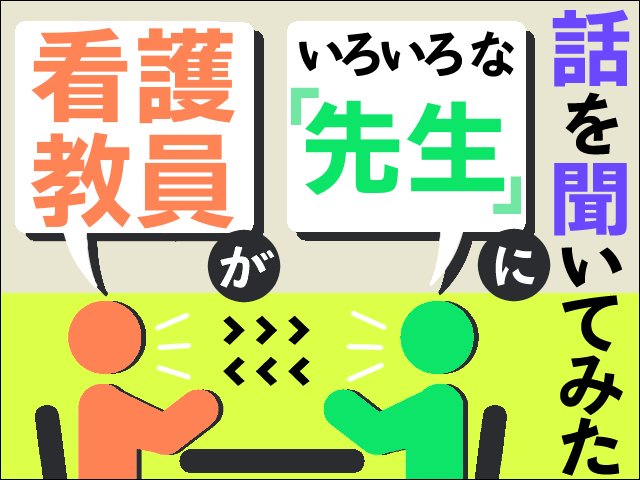

/日本大学教学企画戦略委員会委員/副学長補佐
大学時代(山梨学院大学)はスポーツ競技でインカレ4位、国体3位。世界選手権やワールドカップにも出場したが、大学院では博士後期課程在学中に別個の学会誌に査読論文2本が掲載されるなど、「two way」(二刀流)を目指し続けている。歴史研究、史料論、教育方法論、政治学、社会教育、北欧における教育の研究などさまざまな研究テーマで科学研究費等を受給してきたことが、「個別専門よりも総合的・横断的・教養的」な研究という自分の立ち位置を示していると考えている。

|
インタビューの前に 哲学や倫理学、文化人類学などに代表されるリベラルアーツは、幅広い視点から物事を捉える柔軟な思考力や判断力を育成する基盤となり、看護職を目指す学生は、これを真摯に学ぶ必要があります。それに対し、教員は学生の学びを支援することが大切ですが、その役割を十分に果たすことができていない現状があります。 そこで、教育学を専門とされている古賀徹先生に、リベラルアーツに関する歴史的背景や日本の大学教育の独自性、教育上の課題をお伺いし、看護教育においてリベラルアーツを育む力を伸ばすための示唆を得たいと思いました。さらに、古賀先生の通信での教育経験から、オンラインを活かした教育方法についてもお伺いしました。 |
リベラルアーツと大学教育の変遷
相馬:看護教育では、専門的知識・技術の習得とともに、人に対する共感的態度や多様な考え方を理解する力を身につけることが大切で、それゆえに、人間の本質を探究するリベラルアーツは重要です。しかし一部の学生からは、「看護に関係のない科目は役に立たない」といった発言があり、学ぶことに消極的な様子が見受けられ、教育の難しさを感じます。同時に、私たち教育側は、リベラルアーツを学ぶことの大切さを学生に十分伝えることができていないように思います。看護以外の教育の現場で、同様の問題はないのでしょうか。
古賀:それはあります。自分の目指す領域に関する専門以外を学びたくないという学生は、分野に限らず一定数います。高校生でも「なんで数学を学ばなきゃいけないのですか」「化学をやらなきゃいけないのですか」という生徒がいるのと同じです。ですから、もともと一般教養科目が苦手な子だと、「大学に入ってからもまたやるのか」と落胆したり、「苦手なんですけどどうやれば単位が取れますか」と相談してきたり、出席カード出して逃げるとか代返を頼む学生もいますね。高大連携的な文脈でリメディアル教育などが取り上げられてきたのもこのような流れによるものです。
相馬:人の命にかかわる職業に就く以上、リベラルアーツすなわち一般教養である人間を知る哲学や倫理学、心理学などの学びは、判断力を養ううえでとても大切だと思います。でも学生のなかには、それを学ぶ意義がわからず、「なぜ哲学とか文化人類学、教育学といった専門以外を学ぶのか、なぜすぐに看護のことを教えてくれないのか」といって、最低限の単位しか取らない人もいます。
古賀:専門性が高い分野ほど「この専門を勉強しに来たんだ」という思いが強く、「他は自分に関係ない」と思いがちなので、看護学生のなかにそういう人がいてもおかしくないですね。
私の大学では、リベラルアーツは、私の専門である教育学以外の文学や哲学、史学、理工学など文理融合の学科との共通科目として位置づけられ、1,2年生で履修します。全国の大学はだいたい同じでしょう。そんななか、リベラルアーツを中心とした学問である人文・社会科学は、理系科目に比べて役に立たないものというとらえ方は共通してあると思います。特に、医療系などの高度な職業専門的教育から見たとき、哲学や宗教学、歴史学は地味な感じで、1,2年生のための雑学みたいなとらえ方をされる側面も否定できません。
相馬:看護の大学教育におけるリベラルアーツも、専門科目の前に1,2年で習います。3年制の専門学校教育に比べて4年制の大学教育のほうが教養が身につくと、大学化が進められたときにはいわれたものですが、現実は先に述べた通りです。
古賀:今の大学の4年制教育は、戦後1949年に新制大学が認可されてから開始されましたが、米国型のリベラルアーツを重視する大学の影響を受けています。戦前はヨーロッパ型の3年制で、教養教育はなく、すぐに専門教育となっていました。当時は旧制高等学校が教養教育を請け負っていて、帝国大学進学後の専門教育へとつながっていました。米国は大学院で高度な専門教育を行うと位置づけていて、戦後の新制大学はこのスタイルとなっていきました。もちろん旧来の伝統も残っていて、日本独自の融合した形になっているともいえますが。この米国型では最初の2年間で一般教養を学びますが、日本では1991年の大学設置基準の大綱化で、教員の人件費削減のため教養課程を止めたところが多くありました。さらに、最初の1年間ではなく4年間のなかで単位を取ればいいとするところもでてきて、一時期リベラルアーツは風前の灯火のようになっていました。
相馬:看護教育は、1990年代前半まではヨーロッパ型に近い3年制専門学校が中心でした。専門的な知識・技術の習得に重点が置かれ、いかに現場で即戦力になれるかが教育の目的でした。ちょうど大綱化あたりで看護教育の中心が大学化していきました。それにともなって、専門に特化した内容だけではなく、患者の多角的理解や他職種との協働など、多様な考え方を受け入れるため、人間性を高めるための教養が重視されるようになったのです。
古賀:看護教育が大学化したのは、そういう流れがあったのですね。リベラルアーツが大学教育の象徴のように考えられていたように感じます。
リベラルアーツは、教養を広く学ぶことによって他領域との協働を可能にし、この基盤が現代のイノベーションやノーベル賞受賞につながっています。単にテストの点数を上げる、知識や技術を身につけるだけの「教育」には、人間力を高めることは要求されません。学校では、個性や優しさ、してよいこと・よくないことの判断力、こうあるべきという倫理観など人間性を磨くような人間教育が重要だということです。
相馬:進歩を続けるAIなどを用いた新しい医療技術をどのような倫理観をもって利用するかといった議論のためにも、リベラルアーツはとても重要です。ノーベル賞を受賞したトロント大学のジェフリー・ヒントン教授が、「AIは諸刃の剣みたいなものなので使い方には十分気をつけること、ただ気をつけるには倫理観が必要である」ということをおっしゃっていました。この倫理観を育てる教育がリベラルアーツに含まれると思います。
大学での教育内容とリベラルアーツの位置づけ
相馬:リベラルアーツは、学問として体系化された知識を得る方法以外にも、集団生活のなかで自然と培うことができるものもあるように思います。たとえば、友達や家族など周囲との関係性、祖父母など周りの大人から温かく育てられるなかで自然と身につくイメージもありますが、教育という枠組みにとらわれず教養の基盤はつくられないのでしょうか。
古賀:集団生活のなかで育まれる教養は、必ずしもよいとは限りません。教育学の世界でいうと、第二次世界大戦では学校の思想教育が子どもたちを戦地に送り出したといわれ、教員は戦争を長引かせたことを後悔しました。その教員たちは師範学校で学んできて、そこはまさに専門学校で教養教育がなく教員としての技術だけを学ぶ、絶対教員になるという就職までが義務づけられた学校でした。戦後、米国の教育使節団が来日し、師範学校の反省からリベラルアーツ型の大学教育を推奨しました。そういう面で、日本の教育は米国型になってよかったと思います。
相馬:そうなるとリベラルアーツ教育は、どういう学生を社会に出したいか、どのような大人を育てるかといった国全体の課題にも結びつくことになりますので、やはり学問としての位置づけが重要になりますね。
古賀:ただ、カリキュラムに余裕がないとリベラルアーツはなかなか取り入れることができません。日本の教育カリキュラムは国にがんじがらめに決められて、本当にキツキツで大変だから、多くの大学では共通科目に余計なものを入れることができず、リベラルアーツは後ろ向きになることもあるのではないでしょうか。特に、高度な職業専門的教育では、国家試験を受けるための教育としてコアカリキュラムに基づいています。試験を受けるための授業構成で、1~5限まで全部詰まっていて、ほぼ勉強のことしかない状況です。仲間と触れ合う時間も大切だと思うけど、そういう機会は大学祭しかないといったこともあります。
相馬:確かに、カリキュラムのタイトな詰め方も課題ですね。国が定めている基準の単位数を取らないと卒業要件が満たされず、国家試験の受験資格がなくなり、追いつめられてしまいます。学生たちの関心をしっかり引き出す環境として、学生が自由に時間的な余裕を持って主体的に選べる教育システムの見直しや改善が重要であると思います。
古賀:英国では、大学入学前の準備という位置づけで大学予備教育があり、そこでリベラルアーツを学びます。ヨーロッパの学校制度を見ると、オックスフォードとかケンブリッジの例のように最初に大学がつくられ、そこから子どもにも教育を受ける権利をということで、低い年齢に向けて学校ができていきました。一方米国では、小-中-高-大という順番で、多くの大学は後からできました。高校は準義務教育ですが無償なので、あまり学校に行かない、あるいは卒業しないこともあり、大学で教養を学び直して、大学院につなぐような感じになっています。
フィンランドや米国では、自治体が公立学校の教育にお金をかけていますが、残念ながら日本の行政は教育にあまりお金をかけてきませんでした。自治体判断で高校を無償化しているところもありますが、それは一部で、大きな地域格差があります。さらに研究分野では、日本は壊滅的に人文科学系にはお金を出さない傾向があります。人文科学系がリベラルアーツにつながるものだとすると、国はリベラルアーツに投資していないことになります。
相馬:国によって教育に対する価値観はさまざまで、投資にも大きな差がありますね。国全体の課題をふまえつつ、私たち教員にできること、学生にリベラルアーツの大切さを伝える方法を考えていく必要があるように感じます。
リベラルアーツの育成において求められる教員の役割
相馬:普段、看護教員として専門科目に軸足を置いているので、リベラルアーツにおける実践的な教育はできていません。学生に対してリベラルアーツの大切さの理解を促すかかわりなど、教員が果たすべき役割に課題を感じています。
古賀:私は教職課程の専門科目とリベラルアーツ科目としての一般教養も担当していますが、後者については学生のニーズはバラバラです。「とりあえず単位取るために時間割が空いているので授業をとっています」という態度の人や、「専門職として即席で役立つものをやりたい」といってリベラルアーツを軽んじる人もいます。でも教職の専門科目を取る学生は、教員免許を取りに来ているのですごい食いつきが良く、「教員になるのは大変だよ、責任もあるよ」といった倫理的な話もわかってくれる学生が多いです。そこから総合的な知識・教養の必要性についても理解を促していくことが可能なのではないでしょうか。
そのように考えれば、看護系の大学では、当然専門職である看護師をめざす学生が主でしょうから、専門科目に熱心な学生には、専門性と絡めてリベラルアーツの重要性を働きかけることが効果的だと思います
相馬:先ほども話したように、看護教育は30年ほど前まで3年制の専門学校が中心でしたので、看護系の大学教員のなかには、自身がリベラルアーツを学問として学んでいない人もいます。教員は、病院をはじめとして臨床での経験は必ずあるので、職業的な指導者としては長けていますが、教育者としては不十分だったり課題があったりするのではないかと思います。教員は教育を学問として専門的に学び、幅広い学生理解や教育力を身につけることが必要であるように感じます。
古賀:そうですね。私は高校の教壇に立ってから大学に来ているのですが、「大学教員に教育力がないのは教員免許がないからだ」ということをよく聞きます。大学に自治や自由があるから学習指導要領もないですし。たとえば芸術学部では、専門の芸術家を雇っているような例があり、中学卒業のホンモノの芸術家が講師になることがあります。そういう特色があるととてもおもしろい教育、生きた教育ができると思っています。でも一方、研究者の養成になると修士・博士修了のような高学歴が条件の大学もある。大学や専門分野によって違いはありますが、看護を含む医療では、理論ばかりでなく臨床現場を知っている教員の存在がやはり大切だと思います。
相馬:看護教員にとって臨床経験は必須ですが、実践からは離れているので、病院などでの臨地実習では看護実践する現場スタッフが教育にかかわる両輪の体制です。教育と臨床の乖離は課題の1つです。さらに看護においても研究者の養成は大切ですが、このあたりの教育内容の統制はとれていず、博士課程で学んでいない教員もいます。
古賀:教育系の学会では、今FD・SDやIRなど教育の仕組みや教育力を上げる取り組みをしています。どの分野であろうと、教員には大切なことです。
相馬:教育内容は実践に直結する専門的知識・技術の比重が大きいのですが、リベラルアーツも含めて、まずは教員自らが積極的に学び続けることが欠かせないと感じました。教員として人を育む役割と真摯に向き合い、自己研鑽したいと思います。
さらに、教員が教育力を向上させるためには、時代の変化に柔軟に対応することも大切であると思っています。特にコロナで一気に加速したデジタル化によるオンラインの普及は、看護教育において大きな転機となったように感じています。
オンラインによる教育の多様化
相馬:コロナ禍では教育方法においてオンラインの活用が余儀なくされましたが、今では全面的に対面を中心とした教育方法に戻りつつあります。オンラインは対面とのハイブリッドとしての活用以外はあまり残っていないと感じます。しかし教育の発展を考えると、コロナで経験したオンラインのよさを認め、オンラインと対面の両方の強みを活かした方法を模索する必要があるように感じます。
古賀:本学では2006年頃から、eラーニングなどオンラインを用いた通信教育を行なっています。学校教育法の大学通信教育設置基準では、通信制でもスクーリングという最低限の通学をして対面で学ぶ期間を定めていて、これをオンラインに換えることも認められています。その際も対面授業と同等として質疑応答や添削指導、学生同士の交流の機会を用意することなどが明記されています。同等というのは、いつでも学生と対面し話をする、授業時間以外でも相談を受けることまでやるということです。
相馬:その規定に従って、オンラインでも双方向でやり取りすることを意識しながら取り組むと、ライブ的な授業ができ、かつ意見が出やすい場になりますね。実際に学生からは、オンラインの画面上だと発言や質問がしやすい、書き込みはハードルが低いといった意見もあるように思います。
古賀:オンラインだと質問が出ない場合もあるでしょうが、コメント欄に自由に書き込んでよいとしておくと、案外出てくることがあります。オンラインの授業だからといって、ただ動画をつくって流すのではなく、よい動画をつくることで学生が答える時間を確保すれば対面授業と同等のものができるという結果が報告されています。動画を流しっぱなしで終わりのような状況では、学生は質問できない、コメントがもらえない、友達ができないといったことになります。ただ、普通の授業でも、一方的に話す教員や全然質問に答えない教員がいるので、それをオンラインだけの欠点にするのは違うと思うのです。
相馬:中身が一方通行だと学生は、対面では居眠りされるし、オンラインでは動画を早送りされるから、同じといえば同じですね。動画はどこでも受講でき、資料として何度も繰り返し活用できるよさはありますが。
古賀:いつでもどこでも動画の再生や早送り、早戻しができ、テキストもついて便利だけど、オンライン授業をデジタル黒板のように考えてしまうと、書き込みへのリアクションや提出物に対する手応えがありません。双方向で意見を述べ合える工夫が必要です。
相馬:本学では、赤十字5大学共同で博士課程を設置しており、遠隔にいる学生と教室で出席する学生が同時に授業を受けることができるように、コロナ前からオンラインと対面のハイブリッドで授業を開講しています。オンラインの活用は、対面での出席を必ずしも必要としない方法として有効です。そうなるとオンラインは1つの手段として教育目的に合わせて活用を検討し、対面と併せて双方のよさをうまく取り入れるのがいいと思います。
古賀:オンラインだとなかなか学生同士目が合わない、合っている実感もない、複数で同時にやり取りできないし、表現には限界があります。それが教室だと、どこで誰が何を話しているか意外にわかりますよね。なので、そのツールの限界も知らないといけません。
相馬:そうですね。これまでの会議システムは、1つのグループに入ると他のところを見ることができない、全体が俯瞰できないというのがネックだったと思うのですが、教員含め参加者が色々なグループに入れるシステムができていて、看護系の学会で使われたことがあります。そのときに使われたoVice(https://www.ovice.com/ja)というシステムは、メタバースのようなイメージで教室のレイアウトもでき、人に近づくと話し声が聞こえてくるので、それ聞いてグループに参加するか決めることもできます。会議室にカギをかけて出入りを制限することもできます。動画をつくって流すことだけがICT教育と考えるのではなく、ツールの発展にもアンテナを張っておく必要があると思います。
古賀:会議ツールも1つだけではないですし、デジタルホワイトボードやカード機能を活用すると、マインドマップなどアイデアや発想をまとめることができ、さらに昔からのKJ法やNN法などでも使えそうです。探せばいろいろあるのでしょうね。
相馬:はい。ただ、看護教員のなかには現場で直接話したい気持ちが強く、そういったツールの情報を求めていない、あるいはツールの発展に抵抗がある方もいるように思います。でもそれではコロナの前に戻るだけですね。教育研究で進んでいるバーチャル・リアリティの利用は体験的なので看護との親和性が高く、例えば、看護の多重課題や育児生活の理解など、マルチタスクの現象を空間でイメージし理解できる教育方法を開発している人もいます。最近参加した国際学会では、実際に会場にいるような設定で、アバターで研究発表するなど臨場感がありました。教育方法のさらなる向上を目指して、オンラインの深化に意識を向けたいと思います。
|
インタビューを終えて 看護教育においてリベラルアーツを育む力では、学生への対応を考えるうえで、教育カリキュラムを中心としたシステムにおける課題が明らかになりました。そのようななか、私たち教育者は、学生の学びを支援し成長を促す役割を真摯に受けとめ、自己研鑽を続けること大切であると考えました。また、通信による教育方法の向上では、教育方法における1つの手段としてオンラインの活用を続けることが有用であり、また、教員はさまざまな教育ツールに対して情報感度を高めていくことが必要であると感じました。 今回のインタビューは異なる2つのテーマでしたが、教員の教育力を高めることへの課題は共通しているように思います。 |