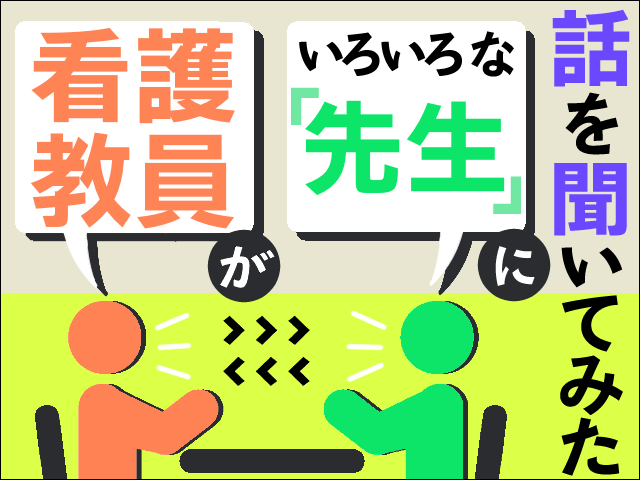- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 教育の基盤
- 教育論
- 教育方法
看護教員がいろいろな「先生」に話を聞いてみた
前野隆司先生に聞く看護学生と教員のウェルビーイングを高める方法
-
 インタビュー
インタビュー
- #ウェルビーイング
- #大学教育
- #幸せの4つの因子
- #看護教員
- 2025/07/25 掲載


1984年東京工業大学(現東京科学大学)卒業、1986年同大学修士課程修了。キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校訪問研究員、慶應義塾大学教授、ハーバード大学訪問教授等を経て、武蔵野大学ウェルビーイング学部長、慶應義塾大学名誉教授。博士(工学)。著書に、『ディストピア禍の新・幸福論』(プレジデント社、2022)、『ウェルビーイング』(日本経済新聞出版、2022)、『幸せな職場の経営学』(小学館、2019)、『幸せのメカニズム――実践・幸福学入門』(講談社、2013)、『脳はなぜ「心」を作ったのか――『私』の謎を解く受動意識仮説』(筑摩書房、2004)など多数。日本機械学会賞(論文)(1999年)、日本ロボット学会論文賞(2003年)、日本バーチャルリアリティー学会論文賞(2007年)などを受賞。専門は、幸福学、イノベーション教育など。

|
インタビューの前に 看護の目的は患者のウェルビーイング(個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあること)を最大化することです。私が前任校で担当していた看護管理学では、看護ケアを質・量ともに最大化するために、看護職のウェルビーイングも同時に探求します。その授業評価アンケートに「今まで、患者を幸福にするためには自分自身を犠牲にしなければいけないと思っていた。しかし看護管理の講義を受けてそうではないと気づいた」と書いた学生さんがいました。私たち看護教員は患者のウェルビーイングを追求するあまりに、看護学生・看護職者のウェルビーイングを置き去りにしていなかったか?と内省し、「患者だけでなく、看護職者のウェルビーイングも同時に探求しなければならない」という思いを新たにしました。 |
「幸せの4つの因子」を高める寄り添い
前田:ご著書で最初に目を引いたのが「幸せはコントロールできる」という言葉でした。私はこれまで幸せは主観的なものだと考えていたので、コントロールできるという考え方が新鮮に映りました。コントロールするためには、ご著書にある『幸せの4つの因子』が基本にあると思いますが、この因子をそれぞれ簡単にご紹介いただけますでしょうか。
前野:4つの因子は、多変量の問題を少ない変数に縮約する因子分析によって求めたものです。
1つ目は「やってみよう因子」で、やりがいや夢、目標、主体性、自己肯定感、成長意欲などに関係します。夢や目標ややりがいをもって、「本当になりたい自分」をめざして成長していくとき、人間は幸せを感じることができます。
2つ目は「ありがとう因子」で、感謝やつながり、利他性、良好な人間関係に関係します。人は孤独感を感じる時に不幸せだと感じます。信頼、尊重、尊敬、愛のある関係性があると幸せです。
3つ目は「なんとかなる因子」で、前向きさ、楽観性、チャレンジ精神、リスクテイクなどに関係します。沖縄では「なんくるないさ」と言いますが、これです。単なる気楽さではなく、やるべき十尾は十分にやったから大丈夫、というような真面目な楽観生が重要です。
4つ目は「ありのままに因子」です。人と比べるのではなく自分の個性を生かして生きることに関係します。自分の軸を持ち、他人ではなく自分との比較でより良い自分になっていける人は幸せです。
心理学の介入研究によって「感謝をする」「自分に優しくする」「理念を浸透させて主体的に働く」「視野を広げる」「ポジティブな言葉遣いをする」など多くの方法が、幸福度を意識して高める方法としてわかっています。要するに、これまで以上に感謝する、チャレンジする、個性を活かす、などの行動を行うことによって、幸せをコントロールできるということです。
前田:それでは、4つの因子をふまえつつ、まず看護職が患者を幸福にするための方法について伺いたいと思います。
ご著書のなかで、「健康が必ずしも幸福の重大因子ではないと」いう記述が印象的でした。疾患や障害があっても幸福な人はいる、というのが先生のお考えですね。
前野:そうです。健康の定義はWHOでも「身体的、精神的、社会的に良好な状態」であり、単に病気がないことではありません。逆にいえば、病気があることイコール不健康ではないということですね。幸福に関しても、疾患や障害があっても「やってみよう因子」「ありがとう因子」「なんとかなる因子」「ありのままに因子」の4つすべてが、全体としてバランス良く高められていれば得られると考えています。
前田:4つの因子をバランス良く高めるために、他者が介入できるヒントのようなものはありますでしょうか。
前野:もちろんあります。「やってみよう因子」なら夢や目標をもつことを促す。「ありがとう因子」なら感謝の気持ちを育むようなかかわり。「なんとかなる因子」ならポジティブな言葉遣いや態度を意識する。「ありのままに因子」なら、人と比べないような声掛けをする。こういった介入が有効です。
前田:日常的に希望をもてる話をしたり、話すときの態度を良くしたりするといったことも含まれるのでしょうか。
前野:はい、まさにそうですね。幸せをコントロールするためには、日々のコミュニケーションで「夢や目標をもたせるような声掛けをする」「笑顔でいる」「前向きな言葉を使う」「大きな声で挨拶する」といった小さな積み重ねが大切です。
まずはやりがい・生きがいを見つけること、そして人とのつながりを大事にすることを推奨しています。たとえば、がん患者の会など、同じ境遇の仲間とつながることも重要です。生きる意味を考えること、感謝の気持ちをもつことが中心だと思います。
前田:学生のなかには、他者とのつながりや感謝を意識するのが苦手な人もいます。そういった学生に対して先生が意識されているかかわり方はありますか。
前野:基本は寄り添う姿勢ですね。厳しく叱咤するのではなく、まずは相手の良いところを見つけて、成功体験を積ませ、エンカレッジ(encourage: 元気づける、 励ます)する。過去に辛い経験があるからこそやる気がない場合もあるので、そこに配慮することが大切です。
前田:学生に対しても患者さんに対しても、困難に直面した際には、立ち止まって一緒に考えるという姿勢が重要だと私も思います。教員として学生にウェルビーイングを伝える際、ただ知識を教えるだけではなく、教員の態度や振る舞いでも伝わる部分が大きいと思いますが、いかがでしょうか。
前野:そうですね。確かに、知識だけではウェルビーイングは伝わりません。幸せは「うつる」んです。これはエール大学のクリスタキス教授も言っていますが、幸せも不幸も周囲に伝染します。だから、教員自身が幸せな人であること、笑顔で優しく、寄り添える存在であることがもっとも重要です。
前田:教員自身がまずウェルビーイングであることが、学生に伝えるいちばんの方法だということですね。
前野:はい、まさにその通りです。私たちは武蔵野大学にウェルビーイングの大学院を新設しようとしています。専門家を育成して、社会全体にウェルビーイングを広めるコア人材を育てていきたいと考えています。
ウェルビーイングの理解を高めるのにエビデンスを示したいが……
前田:残念ながら、看護教員のなかにはいまだに昔ながらの「教えない、ほめない、厳しく指導する教育」が正しいと信じている方もいらっしゃり、対応に苦慮しています。
前野:幸福を高めることを妨げる古い体質のまま厳しい指導を続けている方が現場にいたら、再教育が必要でしょうね。
前田:厳しい教育に対して心理的安全性の重要性を話してみましたが、まったく通じなかったばかりか、残念ながらそれをきっかけに私自身がハラスメントを受けてしまいました。
前野:それは大変でしたね。しかし、心理的安全性も含めたウェルビーイングは、今後ますます重要になっていくと、私は考えています。
前田:厳しい教育が良いと信じている教員に、ウェルビーイングの共通理解を促すのはなかなか難しいのですが、そういう方と何か共有できる良い方法がありますか。
前野:私はエビデンスを示すようにしています。幸せな人は創造性が高く、生産性が上がり、離職率が下がり、健康で長寿にもつながる。こうした科学的根拠を示すと、頭では納得してもらえることが多いです。その後は、ロールプレイングなどを通じて行動を変えていく取り組みが必要ですね。
前田:エビデンスを示し、さらに実践して成果を見せることも大切なのですね。
前野:まずはエビデンスで信じてもらって、次はちゃんと結果が出るような実践をして、結果を出していく。そして、そのほうがいいんだと理解してもらっていくというステップをふむといいでしょう。
前田:「学生がこう言っています」というだけだと、「それは個人の意見である」と返されます。ウェルビーイングが向上していることを、誰でもわかるようなエビデンスで示すとしたら、どのような方法が有効でしょうか。
前野:幸福度は測れますので、アンケートを取って幸福度が向上していればいいですよね。たとえば私の同僚の看護管理学の秋山美紀先生は、セルフコンパッション(self-comassion:自分自身に対して慈しみや思いやりを向けること、自分自身をありのままに受け入れ、大切に扱うこと)を高める介入をすると、幸福度も自己肯定感も高まる、といった結果を出しています。幸福度だけでなく、コルチゾールとかオキシトシンといった生理指標、バイタルデータなど、いろいろな指標でエビデンスは出せます。
介入実験のような形式で行えば明確なデータが取れますが、実際の職場でやる場合は他の要因もからむので、複数人で本気で取り組むことが結果につながるでしょう。もっとも上層部がその気になってウェルビーイングに取り組まないと、下の人たちだけで結果を出すのはかなり難しいとは思います。
前田:そうですね。まさに私も上層部の理解を得られず、「何やってるの」と言われ続けた苦い経験があります。ウェルビーイングに理解のない職場で上層部を動かすには、小さいところから始めていくのが良いと考え、私は自分のゼミの学生への対応から取り組んでいました。このアプローチについてどう思われますか。
前野:ゼミなら自分の裁量で介入ができますから、できる範囲でやるのは良いことだと思います。ただ、大きな範囲で実施できればインパクトも大きいので、できれば病院全体など、広い範囲に波及していくのが理想ですね。
前田:なかなか最初から組織全体のコンセンサスを得るのは難しかったので、小さいところから始めていました。ただ、細かく効果を語ると拒否反応を示す人もいて、コンセンサスを得るのは非常に時間がかかる困難なことだと感じています。先生ご自身がウェルビーイングの話をして、拒否反応を示されることはありますか。「そんなうまくいくわけがない」とか。
前野:ほぼないですね。実際に、創造性が3倍、生産性が1.3倍、売上や利益が伸び、離職率や欠勤率も大きく下がるといったエビデンスを提示すると、科学を信じない人でない限り反論は難しいからでしょう。
ただ、私の場合は専門家として話しているので、より信頼性があるかもしれませんし、そもそもウェルビーイングに関心がある人が私の話を聞きに来る傾向もありますから、興味がない人には届きにくいということを感じる機会が少ないかもしれません。
前田:私は一教員なので説得力の面で不十分だったかもしれません。
たとえば病院でも看護師さんたちが生き生き働いている例もありますし、小学校でも校長先生が学校全体をウェルビーイングな雰囲気に変えたという話もありますから、何とかしたいとは思ったのですが……。
前野:そうですね。病院でも、学校でも、企業でも、トップが変われば組織全体が変わるという成功例は出始めています。先生の現場でエビデンスが集めにくいのであれば、他の良い事例を集め、共有し、学んでいくことが効果的だと思います。
正面からぶつからず、「共感」を駆使する
前田:やはりトップの理解があるとコンセンサスも得やすく、結果も出やすいのはわかっているのですが、なかなか立場的に難しいところもあります。上を動かすにはどうしたらいいのでしょうか。
前野:一般的な組織のなかにもうまく上司を動かす人がいます。たとえば、上司の性格に合わせたアプローチをして、成果を伝えたり、メリットを強調したりする。上司に嫌われたら難しいですが、うまく取り込むことは可能だと思います。
アドラー心理学の平本あきおさんと一緒に『アドラー心理学×幸福学でつかむ! 幸せに生きる方法』という本を書いたことがあるのですが、そこで言われていたのが共感の力です。たとえば、上司が「あいつは何やってるんだ」と言ったら、まず共感する。「そうですよね、大変でしたよね」と受け止める。そのうえで、「あの人の立場に立ったらどう思いますか?」と問いかけていく。相手を責めるのではなく、相手の気持ちに寄り添う。これが変化を促すポイントです。これは相手が上司に限りません。
前田:なるほど。権力をもっている人に真っ向からぶつかるのではなく、共感しながら少しずつ動かしていくアプローチなんですね。
前野:その通りです。権力をもっている人や、エビデンスを示しても反対する人は、自分の考えを否定されると不快と感じやすいということかもしれませんね。そのような場合には、看護学で学ぶと思いますが、アサーティブな接し方をすることも重要だと思います。
前田:私はこれまで、正面からぶつかるような形になってしまっていました。
前野:それは本当にご苦労だったことでしょう。ただ、強い人に対して強くぶつかると、さらに硬直してしまうことがあるので、寄り添うほうが効果的ですね。
前田:本当にそうですね。学生や患者にするように、上司にも寄り添う気持ちをもつことが必要だったと今になって思います。ただ、そのときはそこまでの余裕がありませんでした。
前野:よくわかります。ですが、相手も結局は人間です。弱さもあるし、優しさもある。変わる可能性は必ずあると私は思っています。
態度と行動の積み重ねが説得力を生む
前田:私は、学生の髪型や服装や、何か良い発言をしたししたらすぐに「それすごくいいね!」と、ちょっとでも良いと思ったらすぐ口に出してほめるようにしているのですが、これは効果があるでしょうか。
前野:好意的なフィードバックを意図的に行って、ウェルビーイングを高めるのはとてもよいことです。
私の同僚の先生も、学生の良い発言には「いいね」と心からほめています。努力や挑戦など、内面の良さにも気づいてエンカレッジすることが大切です。前田先生が実践されていたことは、まさに正しい方向だと思います。ただし、外面をほめるのはハラスメントになることもあるので注意が必要です。
前田:ありがとうございます。無理にほめるのではなく、努力や成長のプロセスに肯定的なフィードバックを送ることを意識していました。ただ、それでも「嘘くさい」と感じる学生もいるなと感じています。ウェルビーイングに抵抗感をもつ人たちにはどう接すればよいでしょうか。
前野:嘘がなければうさんくさくはなりません。本当に思っていることを本気で褒める。もし嫌な面が見えたときには、良い面を一所懸命探してポジティブな声掛けをする。それができれば、繊細な人たちにも伝わるはずです。
うさんくさがる人に対しては、逆に「うさんくさいと思ってるよね。でも私も本気で言ってるんだよ」と伝えると、少しずつ距離を縮められます。私も20年前はうさんくさがられていました。でも今では、理論武装とエビデンスを整え、誰の懐にでも飛び込めるようになり、うさんくさがられることはなくなりました。
ウェルビーイングの実践は「正義」です。疑われても、絶対に間違っていないと信じ続けることが大切です。
前田:確かに私も真っ向から「これが正しい」と戦うような姿勢になってしまっていたかもしれません。もっと穏やかに、自分の信じるやり方をコツコツ実践していくべきだったと反省しています。
前野:私も昔は戦っていました。でも、戦うよりも「北風と太陽」の太陽のように、温かく接する方が効果的だと気づきました。北風ではなく太陽で、少しずつ相手を動かすほうが疲れません。
前田:北風と太陽の話は、学生にもよくしています。患者さんにはできていたのに、強い上司をはじめとした、他の人には実践できていなかったと痛感しました。
前野:患者さんや学生には自然にできるけれど、上司には難しいのは当然です。でも、上司にも同じように対応できるようになれば、怖いものはなくなりますよ。ぜひ、少しずつ範囲を広げてください。
前田:今日の話を通して、自分自身の在り方を見直す大きなヒントを得られました。ウェルビーイングの効果を信じて、信念をもって実践し続けることが重要だと改めて思います。
前野:はい、その通りです。看護にはすでに素晴らしい理念、アサーションや患者中心のケアなどが存在しています。それを患者さんだけでなく、同僚や上司に対しても広げていくことがこれからの課題ですね。
前田:学生にも、言葉だけでなく、態度と行動でウェルビーイングを示していきたいと思います。その積み重ねが、次世代の看護をより良いものにすると信じています。
前野:はい、応援しています。ぜひ一緒に共同研究しましょう。私たちの学部には、看護管理学出身の先生もいますし、連携できると思います。ウェルビーイングが実際に職場を良くするエビデンスを、ぜひ一緒につくっていきましょう。
|
インタビューを終えて 「幸福の4つの因子」はウェルビーイングな状態を生み出すためのヒントで、4つの因子をバランスよく伸ばしていく、という考え方が印象に残りました。個人の経験則ではない、研究に裏付けされたエビデンスがあることは、実現可能性が高い方法だと確信して実践することができ、また同時に他者への説得力をもつのだ思います。改めて研究結果をコツコツと積み重ねることの重要性も再確認することができました。 しかし一方で、「教えない教育、厳しい教育が正しい」という信念をもつ教員に働きかけることの難しさも、改めて浮き彫りになったように思います。 教えない教育(伝統的徒弟制:親方は教えず、弟子が試行錯誤を繰り返しながら技術を習得する教育法)よりも、教員が適切なガイドをしつつ、学生(学習者)が考えるプロセスを支援する「認知的徒弟制」の方が有効であること、心理的安全性が高い環境ではより学習効果が高まることは、既に研究されエビデンスも明らかになっています。ただ、大上段で真正面からエビデンスを振りかざしても、拒絶反応を招くだけなのだという反省もありました。無理に説得するのではなく、まずは自分自身も含めたウェルビーイングを高めること、周囲の人にも小さなことから働きかけること、そしてその結果、「なんか楽しそうにうまくやってて、成果も出してる」と思われ、自分もそうなりたい、と思わせることが、結果的に全体のウェルビーイングを高めることにつながるのだと改めて感じました。エビデンスを上手く活用しながら、患者・看護師・学生・教員がともにウェルビーイングな状態になるような教育実践を考え、実践してゆきたいと思います。 |