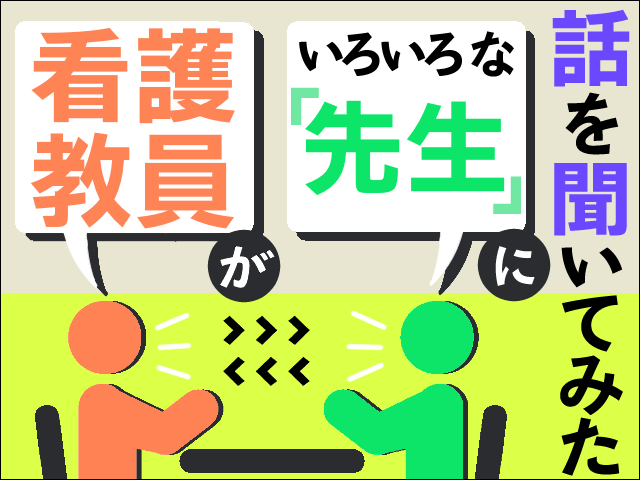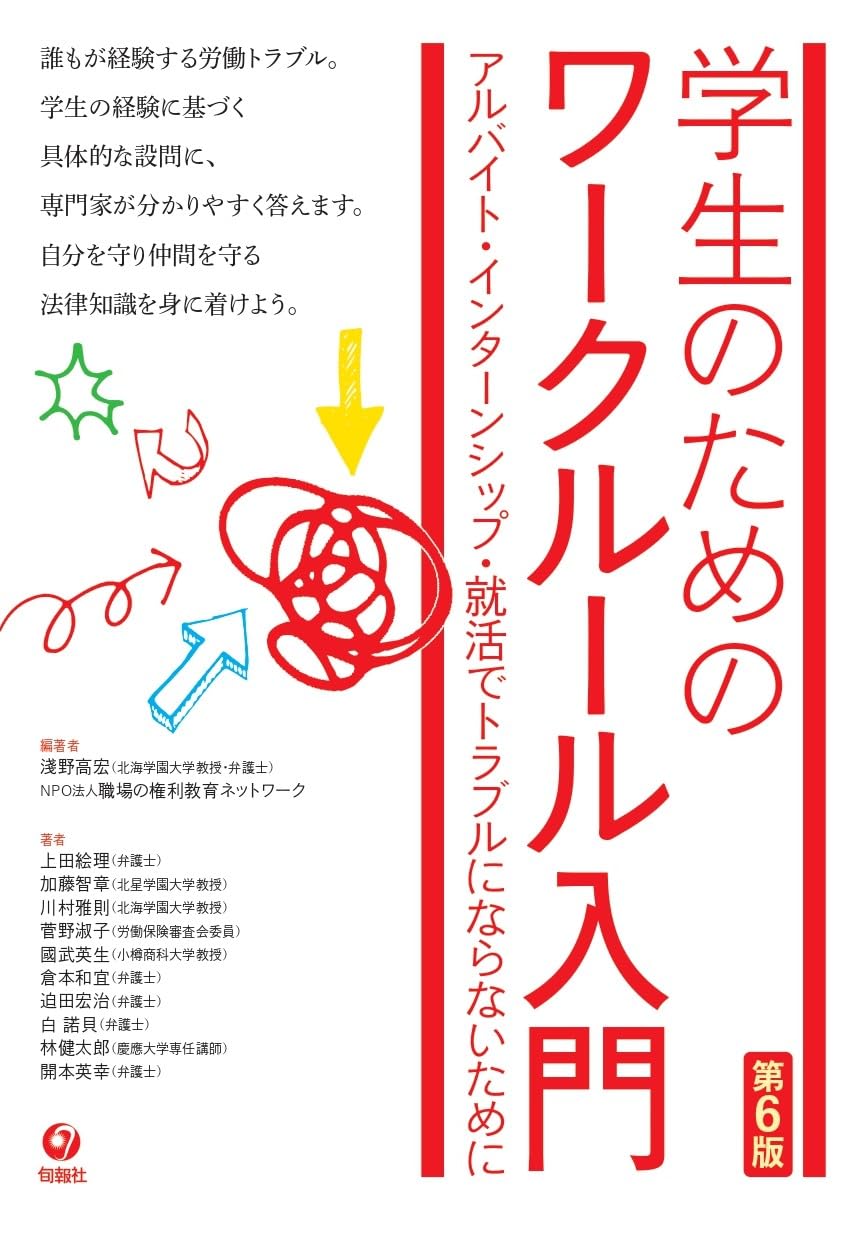- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 教育の基盤
- 教育論
看護教員がいろいろな「先生」に話を聞いてみた
淺野高宏先生に聞く 「看護師として働くこと」「看護教員として働くこと」を自覚するための ワークルール
-
 インタビュー
インタビュー
- #ワークルール
- #働き方改革
- #職場づくり
- 2025/11/07 掲載
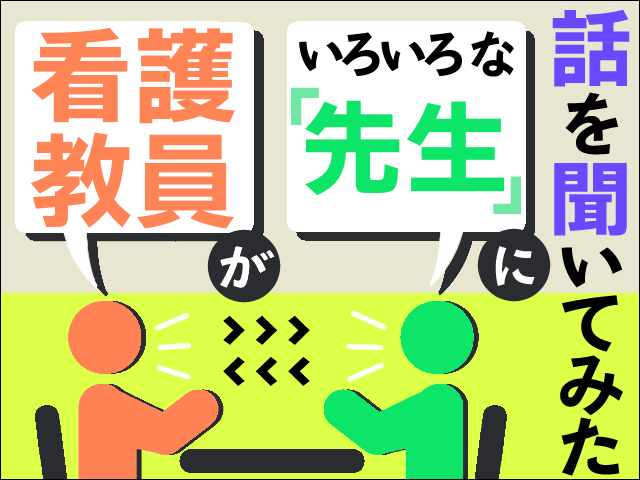

ワークルールの第一人者として、理論と実務の両面から現代社会の労働問題に取り組んでいる。特に「労働契約上の使用者による労働時間把握管理義務」や「労働者の同意による労働条件不利益変更」といった、日々の業務におけるワークルールの根幹にかかわる課題に対し、長年の研究と豊富な実務経験に基づいた見識は多方面から高く評価されている。NPO法人職場の権利教育ネットワークの理事も務める。
著書:『学生のためのワークルール入門 第6版(共編著)』(旬報社)『18歳から考えるワークルール 第3版(共著)』(法律文化社)『労働法の基本 第3版(共著)』(法律文化社)など

|
インタビューの前に ワークルールは、働く際に知っておくべき法律やルールのことです。たとえば、労働時間の上限や最低賃金、有給休暇の取得など、労働者の権利を守るための決まりが含まれます。これらを理解することで、不当な扱いを避け、安心して働くことができます。 厚生労働省の調査によるとアルバイトをしている学生の60.5%が労働条件などで、何らかのトラブルを経験しているとされています。特に労働時間の問題や職場の人間関係に関するトラブルが多いようです。また、看護教員のワークルールには労働環境の整備やワークライフバランスの確保が重要なポイントとして挙げられます。看護系大学の教員は、教育・研究・実習指導など多岐にわたる業務を担うため、適切な勤務条件や公正な評価が求められます。 ワークルールは、企業や組織によって異なりますが、十分に浸透していないケースが多いと指摘されています。特に、労働者と使用者の双方がワークルールの知識をもっていないことが原因で、適切な労働環境が確保されないことがあります。ですので、看護の臨床現場、教育現場でも、ワークルールの知識は重要だと考えました。 そこで、ワークルールを専門とされている淺野高宏先生にお話を伺うことにしました。 |
内山:まず簡単に自己紹介をさせてください。私はもともと看護師としての勤務期間が長く、現在の大学教員としてのキャリアは2016年から始まりました。それ以前は病院で看護師長として病棟を担当しており、労務管理などにも携わっていました。今は看護学生をこれからの社会に送り出す立場にあります。看護学生のなかには、学業と並行してアルバイトをしている学生も多くいます。実習中にも学生から「バイトが休めなくて無理をしてしまい、体調を崩してしまった」という声を聞いたことがあります。今は“働き方改革”が進められていますが、現場では「限られた時間のなかで、どうやって仕事をこなしていくか」という課題に日々直面しています。
私自身、現在は大学教員として裁量労働制の下で働いていますが、この「時間をどう管理するか」という点は、非常に難しさを感じているところです。もちろん、働くためのルールがあることは理解していますが、実際の職場では、そのルール通りにはいかないことも多いものです。権利を主張することもできると頭ではわかっていても、それが職場内の人間関係や実際の業務においてスムーズにいくとは限らない、という難しさがあります。
今日は、これから社会に出ていく学生たちに、働くうえでの「知恵」や「力になる知識」をどう伝えていけるか、という観点に加えて、実際に現場で働いている私たち教員自身が、裁量労働制の下でどう働いていくかという視点からも、お話を伺えればと考えています。
淺野:私は、弁護士として労働関係を中心に活動していた実務的な実績から大学に誘われ、現在は大学で教鞭をとり研究を行いながら、弁護士活動も続けています。
弁護士活動のなかで、何らかの事件の当事者と話していると、もう少し基礎的な知識が事前にあれば、こんなにトラブルは大きくならなかっただろうと思えるケースはたびたびありました。大学でも、学生がバイトに関して「変だな」「モヤモヤするな」とは思いながら、何が変で何がモヤモヤの原因かが言語化できずに、ただただ不満を内に溜めるだけで問題を解決できず、我慢するかやめてしまうという選択肢しかないという状況も経験しました。
人間関係は楽しいし仕事はおもしろいけれども不満が溜まってしまうというときに、その原因が、たとえば労働条件だったり職場のルールだったりしても、知識がないと「それはおかしい」と指摘できませんね。その結果、離職になってしまうのは、残念なことだと思います。何がおかしいかを知るための基礎知識、法律的な基礎知識がないと、「これこれに反しているからおかしいです。だから変えてもらえませんか?」という発想は浮かんでこない。なので、こういう職場でのモヤモヤみたいなものを改善する方向に向けるため、ワークルールを市民教育という形で知ってもらう活動も行っています。
時間外労働と“前倒し残業”の現実
内山:看護職においても、近年は「働き方改革」の流れのなかで、時間外労働やサービス残業に対する考え方を刷新する必要があります。特に病院では、「残業をしないように」と言われるようになっています。これはもちろん、働く人の健康やワークライフバランスの観点から見れば、大切な取り組みです。しかし一方で、こうした制度の枠組みによって、現場では新たなジレンマが生まれています。たとえば、看護師として「患者さんの役に立ちたい」「もっと良い看護をしたい」と志を持って就職した卒業生たちが、「時間内にすべてを終わらせなければならない」という制限のなかで、本当にやりたいことができずに、もどかしさを抱えているケースが少なくありません。その結果、「自分は何のためにこの仕事に就いたのか」とやりがいを失い、離職につながってしまう現実もあるのです。
若い世代のなかには、仕事は仕事としてきっちり時間で割り切って、オンとオフをしっかり切り替えて働きたいと考える人もいます。一方で、「看護師として患者さんのために尽くしたい」「たとえ時間外でも自分がしたいケアがある」と感じる人もいる。この“価値観の多様性”があるなかで、「定時で帰ることが絶対」という一律の働き方が、必ずしもすべての人の納得や満足にはつながらないという課題が浮かび上がっています。
私自身の経験からも、業務を効率よく、丁寧にこなすためには、勤務が始まる前に情報収集をして、スケジュールを立てておく時間がどうしても必要でした。しかし今では、それも“前倒し残業”とみなされ、「早く来て準備してはいけない」ので、結果として、頭のなかが整理できないまま、慌ただしく一日が始まってしまうのです。
看護の仕事は、ナースコール、患者さんからの声かけなど、常に予期せぬことが起きる現場です。なのに、あらかじめ準備しておく時間に看護師の個別性が認められないというのは、看護師にとっても患者にとっても不利益につながるのではないかと考えています。
淺野:お話しいただいた状況に関して、まず法律の観点からお話しします。たとえ職場から明確な指示がなかったとしても、業務に関連する準備行為が職場内で行われ、それが黙認されているような状況であれば、それは「労働時間」と見なされる可能性が非常に高いと考えられます。
たとえば、「早く来て情報収集しておいてくれたら助かる」といった空気があり、それを組織側が認識しつつ放置している場合、形式的には「自主的」とされていても、法的には指示と同じようにとらえられることがあるのです。労働時間の枠組みを定める労働法の基本的な立場としては、「睡眠や生活時間をしっかり確保したうえでの労働」という前提に立っています。つまり、「誰が好き好んで、やる必要もないのに早朝から職場に来たり、夜遅くまで残っているだろうか。そこには何らかの業務目的があるはずだ」と考えるわけです。そうした“前倒しの労働”が積み重なれば、「それは使用者の指示のもとに行われた労働」と評価され、残業代の支払い義務が生じることになります。現在、未払い残業代の請求は、法律上は5年まで遡れますが、当面は3年分をさかのぼって請求することが可能です。ですので、病院などの現場では「トラブルになるくらいなら禁止しよう」という判断をしているケースが多くなっているのが現状です。これは法律的には正しい対応だといえるでしょう。
ただし、現実には看護師や弁護士をはじめとする専門職では、資格を取ったからといって、すぐに一人前としてすべてをこなせるわけではありません。実務のなかで先輩の背中を見ながら学び、現場で場数をふむことによって成長していく必要があります。
看護師の皆さんであれば、患者さんとのやりとり、医師との連携、多職種との協働といった日々の実践が、知識と経験を蓄積する貴重な機会になります。若いうちは、そうした機会を“シャワーのように”浴びながら、徹底的に仕事に浸かって学ぶことが、専門職としての土台を築くうえではとても大事なことなのでしょう。
しかし、今の労働法の基本は「○時から○時までここにいて、言われたことをやりなさい」という“指示労働”(これを「従属労働」と呼んでいます)を前提として、労働時間を規制するという設計になっています。ですから、自分で考えてスキルを磨き、積極的に動いていきたいというタイプの人には、やや窮屈に感じられる制度かもしれません。
一方で、「やる気があって、使命感をもって働いていた人」が、気づかぬうちに疲弊し、ある日を境に回復できなくなって、失敗が重なり、自信を失い、やがて精神的に追い詰められていく――そんな事例も、現実には数多くあります。なかには、身体や心の不調から退職を余儀なくされる人、最悪の場合には命を落とすような事態に至るケースもあります。
こうした「やりがい」と「健康・安全」のせめぎ合いのなかで、どこに線引きすべきかは非常に難しい問題です。労働法がすべてを解決できるわけではありませんが、少なくとも、そうした“歯止め”としての役割を担う必要があるのだろうと思います。
ですから、内山さんがご指摘されたように、意欲的に働きたいという人にとって、現行の労働法が「足かせ」と感じられる部分があるというのは、その通りかもしれませんね。
現場に求められる「賢さ」と、注意すべき同調圧力
内山:そう考えると、やはり私たちはもっと“賢く”ならなくてはいけないのだろうと感じます。たとえば、病棟の師長や労務管理の担当者からは、「サービス残業になるから、早く来ても電子カルテを開かないでください」と言われることがあります。それは、法律的にも組織的にも妥当な対応なのでしょう。でも、実際には仕事を円滑に進めるために、勤務開始の30分前くらいに来て情報収集をしておきたい、という看護師もいます。もちろん、1時間も2時間も早く出勤するわけではありません。短い時間であっても、その“ちょっとした準備”によって、自分の仕事がスムーズに運び、患者さんによりよい看護が提供できる。そういう実感があるからこそ、早めに来て段取りをつけておきたいという人がいます。このような働き方については、一律に「禁止」とするのではなく、「自分が仕事をしやすくなるために、自主的にしている行動」であれば、もう少しおおらかに認めていく、そういう柔軟さが必要なのではないかと思うのです。もちろん全員に強制するのではなく、やるかどうかは各人の判断に委ねる。そのうえで、「それなら必要な時間だよね」と受け止められるような職場文化が、これからは求められていくのではないでしょうか。
私たちも、ただ生真面目に働くのではなく、制度やルールを理解したうえで、自分の身を守りながら、やりがいのある看護を続けていく。そのための“賢さ”が、これからの看護職にはより一層大切になっていくように感じています。
淺野:内山さんがおっしゃるような、ある程度柔軟に対応する現場の工夫というのは、うまく機能すれば非常に理想的だと思います。たとえば「この時間からこの時間までは、自主的に来てもらって構いません」「その時間に情報収集や段取りをしたい人はしてもいいですよ」という運用であれば、強制ではなく、来ない人にペナルティもない。そうであれば、その時間は法律上“労働時間”とは見なされないという扱いも、法的には一応可能です。ただ、問題はそこから先です。実際には、現場に熱心な人が多いと、「ほとんどの人が来る」という状況になりがちなんですね。そうなると、形式上は自主的でも、実質的には「行かないと変に思われる」「新人なのに来ないのか」といった、いわゆる“同調圧力”が生まれてきます。
そうなると、最初は本当に自由参加だったはずのものが、いつの間にか「暗黙の義務」になってしまう。それが何年か続くと、「うちの病棟はそういう文化だ」「新人は早く来て準備するものだ」というように、“伝統”のようになってしまうわけです。すると、本来の「自主性に任せる」精神からどんどん離れていってしまう。これが現場でとても起こりがちな構図です。
ですから、制度上あるいは文化として「自由参加」でうまく回るのであれば、非常に良いことですが、それをどうやって“自由のまま保ち続けるか”がとても難しいのです。そこを維持するためのマネジメントや組織的な工夫が本当に実現可能なのか、今後ますます実態に即した検証と工夫が求められるところではないでしょうか。
内山:確かに難しいですね。私がかつて看護師長として現場の労務管理を担当していたときには、たとえば「おはようございます」と朝礼をしてから、「ではこれから15分間は情報収集の時間です。各自で自由に使ってください」というようなかたちで運用していたことがありました。これは、今でいう働き方改革のずっと前から、サービス残業はよくないという問題意識があって、「どう工夫するか」という試行錯誤の一環でした。あくまで形式上はその15分間を“自由時間”として設定し、あまりガチガチにはせずに柔軟に運用しようとしていたんです。
でも、先ほど淺野先生もおっしゃっていたように、ベテランであればその15分で必要な情報をスムーズに把握できても、経験の浅い看護師たちは、そもそも「何を」「どのように」情報収集すればよいのかも手探りの状態ですから、15分ではとても足りないということもあるんです。
ですから、「15分間ね」と一律に決めてしまうと、それがかえって負担になってしまう人たちも出てきます。そういった個人差や成長段階の違いをどう吸収していくかという点でも、本当に現場は悩ましい。特に、「仕事前の準備時間」というものをどう位置づけ、どう運用するのか、これは、労務管理と看護教育のあいだにある、非常にデリケートな課題だと思います。
「残業ゼロ」のルールと実際の臨床現場のはざまで
内山:病院では、「仕事終わり」にあたる時間帯の残業についても、制限されるようになってきています。これも働き方改革の流れのなかで「残業をさせない」という方向性が強まっていること、また残業代が通常賃金の1.25倍(125%)にあたるため、病院としても人件費を抑える必要があるという経営的な背景があるのだろうと思います。
つまり、経営上の「残業をしないほうが望ましい」という判断のもとに、現場に「うちは残業ゼロですから」と伝えられる場合があります。それが、病院の健全経営や良質な労務管理の象徴のようにとらえられている場面も見受けられます。しかし、その結果として、誰がそのしわ寄せを受けているかというと、患者さんだったりするのではないかと危惧しています。
これはもはや、単なるワークルールや労務管理の問題というよりも、看護の「仕事をどうつくっていくか」という本質的な問題ではないでしょうか。残業をしてはいけないからといって、本来やりたいと思っていた仕事、患者さんのためにやりたかったケアができずに終わってしまう。そうしたもどかしさを感じている看護師もいるようです。
もちろん、「決められた時間内で仕事を終える」というのは、労働のルールとしては基本であり、あるべき姿なのだと思います。ただし、それが本当に意味のあるルールとして機能するためには、職員がきちんと「指示を受けたうえで働く」という形が整っている必要があります。もし、明確な指示もなく、「残業してはいけない」だけが先行してしまえば、やりたい仕事にブレーキがかかり、患者ケアの質が下がることにもなりかねません。だからこそ、ルールのなかで的確な指示と判断ができるような職場体制を整えることが、これからの看護の現場には求められているのだと思います。
淺野:内山さんのお話を伺っていて、これは看護師に限らず、弁護士や医師をはじめとする他の専門職にも共通する課題だとあらためて感じます。専門職というのは、ただ業務をこなすだけではなく、「じっくり考える」「整理する」「調べる」といった知的な作業、つまり専門性を深めるための時間が不可欠です。
しかし、勤務が始まると、現場は一気に慌ただしくなります。電話が鳴る、呼び出しがある、対応に追われる……。これは私たち弁護士の世界でも同じで、クライアントから突然電話が入り、案件の指示を次々と求められる。そんな中で腰を据えて文章を書いたり、資料をまとめたり、研究したりといった時間は、なかなか取れません。
だからといって、単純に労働時間を延ばせば良いという話ではありません。むしろ、その「枠のなか」でどうやって集中できる時間を捻出するかという発想に切り替える必要があります。そのためには、分業の工夫が求められるかもしれません。たとえば、これまで1人の専門職がすべて担っていた電話対応や呼び出しなどを、第一次的には別のスタッフが受け持つ仕組みに変える。あるいは、AIやロボティクスといったテクノロジーを活用して、煩雑な業務を補完していく。そうした環境整備によって、本業に集中するための時間を、限られた労働時間のなかでどう確保するかが問われているのだと思います。
私も入院経験があるのですが、本当に看護師の皆さんは献身的に働かれていて、こちらが心配になるほど常に動き回っておられました。その姿からはプロフェッショナルとしての誇りや使命感を強く感じましたし、非常に感銘を受けました。ただ同時に、それはまるで「超人的な働き方」でもあると感じました。つまり、本来1人の人間が担うには過大すぎる量の業務を、専門職という名のもとに、当然のこととして背負っているようにも見えたのです。そうした現場の実情をふまえれば、「雑務」と簡単に片づけられない業務であっても、何らかの分担や仕組みの見直しを通じて、専門職が専門性を発揮できる時間と空間を確保する必要があります。現状は、人手が不足し、休みも十分に取れないなかでやりくりしているのが当たり前で、それは非常に困難な課題でもあります。
それでもやはり「どうにかしなければならない」という意識をもつことが、働き方改革の本質的な方向性でもあるはずです。現場の努力に比して、テクノロジーや制度がまだ十分に追いついていないというのが現状ですが、それでも希望を持って模索していくことが求められているのだと思います。
ワークルールの理解と、順守に必要な職場づくりのデザイン
内山:いま私たちはワークルールについて話していますが、あらためて感じるのは、これは単にルールを守るということだけでなく、「自分たちの職場をどうデザインしていくか」ということに直結しているという点です。
それぞれの立場によって、見える景色や重視するポイントは異なります。新人の立場、中堅の立場、病棟をマネジメントする立場、さらには看護部全体を運営する立場。立場が変われば、求められる判断や配慮のバランスも当然変わってきます。どの立場にあっても共通して土台となるのは、やはり労働法をはじめとする基本的な法的枠組みの理解です。私たちは法律の下で働いており、その理解があってこそ、自分たちの職場をより良くするための工夫や改善が可能になります。単に「これだけやっていれば法的に問題ない」という最低限の対応で済ませるのではなく、「人としてどうあるべきか」「どうすれば健康と尊厳を保ちながら働き続けられるのか」を考えなければなりません。
1人ひとりが国民としての権利を持ち、同時に職業人としての責任を果たし、なおかつ人間らしい生活ややりがいを維持していくためには、法律を上手に活用しながら、職場をきちんと設計していくことが必要です。淺野先生のご指摘を伺いながら、私自身も改めて「しっかり考えて、主体的に職場をデザインしていくことが大切なのだ」と感じました。
淺野:その通りですね。労働法の制度や運営に関してヨーロッパ諸国を訪れた際に感じたことがあるのですが、それは働き方の「余裕」の違いです。たとえば、ヨーロッパの裁判官や弁護士などの専門職も一定の時間は働いているはずですが、全体的に業務の流れが非常に落ち着いていて、時間的なゆとりがあるという印象を受けます。お店に行っても、営業時間が「8時間」と決まっていれば、終了時刻には本当にシャッターが閉まっている。日曜日に休みと決めれば、町中のお店がほぼ全部閉まっていて、それが当然とされている。むしろ「日曜営業はルール違反」と捉えられるような空気すらあって、休むときはしっかり休む、時間が来たらきちんと帰るという文化が根づいているのを感じます。もちろん不便を感じることもあるのですが、皆が同じ条件で働いているからこそ、それに慣れ、納得して暮らしているのだと思います。
実際、日本の労働時間に関する法制度も、そのルーツは多くがヨーロッパの制度にあります。ただ、日本はそれを単純に移植できる国ではありません。日本人は非常に真面目で、少しでも良い仕事をしたいと努力し、手を抜くことを前提にしない国民性があります。だからこそ、労働時間という枠のなかでどう良い仕事をするかという点について、多くの人が悩み、模索している。その悩んでいる姿こそ、仕事に真剣に向き合っている証拠とも言えるかもしれませんが。
でも、やはり大切なのは、労働時間のなかで「自分の仕事に集中できる」「自分のやっていることに納得ができる」と実感できる環境をどうつくるかだと思います。仕事の割り振りの工夫はもちろん、現場に任せきりにせず、職場で生じるトラブルや悩みをすべて現場の担当者が抱え込まない体制を整えることも必要です。そういった負担を別の人が担えるようにする、あるいは外部との連携やサポート体制を構築して、専門職が本来の業務に集中できる環境を整える。そうした「職場設計」の視点も、あわせて考えていくべき時期に来ているのだと思います。
雇用形態の多様化に向き合うために必要な知識と姿勢
内山:そうですね、今は、社会全体でさまざまな働き方が認められるようになり、雇用形態も多様化しています。たとえば、パートタイムや契約社員、派遣、フリーランスなど、ライフステージや個人の事情に合わせて選べる選択肢が増えてきています。看護の現場でも、多様な働き方ができることで、スキルアップの機会が広がったり子育てや介護との両立がしやすくなったりするなどのメリットがたくさんあります。一方で、雇用が不安定だったり、同じ仕事をしていても待遇やキャリアパスが異なったりと、現場での不公平感やモチベーションの低下につながるなどデメリットも存在します。
だからこそ、私たち看護職に限らず、誰にとっても重要なのは、「自分の働き方」について、自分自身がしっかりと理解しておくことなのではないでしょうか。「誰かが説明してくれるだろう」とか「病院がきちんとやってくれているはず」とかではなく、それぞれが主体的に、必要な知識をもっておくことが大事だと思うんです。
そこで、労働と法律の専門家である淺野先生にお伺いしますが、多様な雇用形態がある今、「これは必ず理解しておいたほうがいい」という基本的でかつ大切な知識や視点があれば教えてください。
淺野:今のように多様な雇用形態が存在するなか、皆さんにぜひ押さえておいていただきたい重要なポイントが2つあります。
1つ目は、「正規から非正規への切り替えが、安易に行われてはいけない」という点です。たとえば、ある方がフルタイムの正規職員として長く勤務してきたとします。ところが、結婚・出産・育児・介護などのライフイベントを迎えることで、これまでのようにフルに働くことが難しくなった。このような場合に使用者(雇用主)から「それなら非正規に切り替えてください」と一方的に言われるケースがあります。しかしこれは、労働法の観点から見ると、単なる勤務時間の変更ではなく、「退職の強要」や「解雇して再雇用する」という行為に近い場合もあります。つまり、労働条件の変更は決して軽く見てはならない重大な問題だということです。正規職員であることには、「育児・介護休業」「年次有給休暇」など、法的に保障された多くの制度をフルに活用できる権利が含まれています。これらの権利行使を理由に非正規化されたり、不利益な扱いを受けたりすることがあってはなりません。正規職員とは“超人のように”フルで働ける人のこと、という考え方は誤りであるということを、まず知っておいていただきたいと思います。
2つ目は、もともと非正規として採用された場合の処遇の問題です。看護職のなかには、はじめからパートや嘱託、契約社員、あるいは派遣社員など、非正規雇用で働いている方も多くいます。この場合に重要なのが、「同一労働同一賃金」(均衡待遇・均等待遇)の原則です。これは「パート・有期雇用労働法」(通称「パート有期法」)に明記されており、同じ仕事をしているにもかかわらず、雇用形態の違いだけで賃金や待遇に大きな差があることは、不合理な格差として認められないというルールです。もちろん、業務内容や責任の範囲、就労時間、雇用期間などに違いがあれば、その違いに応じた差は認められます。しかし、看護職のように、雇用形態にかかわらず同等のスキルや専門性が求められ、実際に同じような業務に従事している場合には、「特定の手当が一切つかない」などの一方的な格差は、不合理である可能性が高く、「賞与がゼロ」「退職金がない」といった待遇差についても法的に問題とされるのです。
以前であれば「契約書に書いてあるので差があるのは当然です」と言われて終わっていたかもしれませんが、現在は法律により、事業主にはその格差の合理的な理由を説明する責任があるとされています。つまり、「なぜ私にはこの手当がないのですか?」と聞かれた際に、明確な説明ができなければ、それは不当な格差と見なされる可能性があるのです。こうした場合、裁判まで進めば、その差額を損害賠償として請求することも法的には可能です。ですから、非正規であっても「なぜこの待遇なのか」という疑問をもったときには、説明を求める権利があるということ、そしてその疑問に対してきちんと納得できる説明が得られない場合は、改善を求めることができるということを、しっかり理解しておいていただきたいと思います。
内山:働くうえで最も基本的なことの1つは「労働条件を正しく理解する」ということだと私も思います。おっしゃるように、まずは自分がどのような条件で働いているのか、あるいはこれから働こうとしているのかということを、自分自身の目でしっかり確認し、理解したうえで選択することが何よりも大切です。
これは、学生時代のアルバイトにおいてもそうですし、卒後の就職においてもそうですね。誰かに任せてしまうのではなくて、自分の責任として労働契約や雇用条件などの「文書」をしっかり読み、納得して働き始める。この姿勢が、自分の働き方を守るための出発点になるのだと、あらためて感じました。もし働くなかで「これっておかしいのでは?」と疑問をもつような場面があったときに、自分がどんな権利をもっているのかを知らなければ、その権利を守ったり主張したりすることもできません。だからこそ、これから社会に出る学生たちにも、「わからないままにしない」「人任せにしない」「自分のことは自分で知る・選ぶ」という姿勢を大事にしてほしいと思います。
淺野:「権利」というと法律の難しい話のように思われがちですが、実は、法律の知識をもち出す前のもっと身近なところ、たとえば「労働契約書」や「労働条件通知書」「就業規則」にその出発点があります。自分がどんな条件で働くことに合意したか。そこを正しく知ることが、働くうえでのすべての基本です。しかし実際には、自分の労働条件をよくわからないまま「とりあえず働いている」という方も少なくありません。これはもったいないですし危険でもあります。働くということは、やりがいや自己実現ももちろん大切ですが、同時に「賃金を得る」「健康を維持して一定の労働時間のなかで働く」「休暇を取る」といった具体的な条件の下で、契約の枠内で行われる行為だということにも注意を向けていただくことが重要です。ですから、労働条件については納得するまでしっかり確認していただきたいと思います。
労働契約において「合意していないこと」や「契約に書かれていないこと」を後から当然のように求めることは、本来できません。合意内容が法律に違反する内容であれば別ですが、そうした場合でなければ、合意に基づいた労働条件が尊重されます。ですから、「今の自分の労働条件をしっかり把握しておくこと」は、どんな働き方であっても、自分の働き方を守るための出発点になります。これは看護職に限らず、どんな職種にも共通する大切なポイントだと思います。
内山:看護という専門職の教育においては、つい「専門的な知識」や「技術の習得」に力点が置かれがちです。もちろんそれは大切ですが、働く以上は、労働のルールすなわちワークルールに関する教育も、もっともっと高い比重で扱われるべきだと強く感じています。やはりこれは、教員が学生に必ず伝えていきたいことですし、自分自身が働いていることもふまえて、考え続けなければいけないテーマだとあらためて感じました。
専門業務型裁量労働制の活用と休職への対応
内山:ここでまた、「働き方の制度の多様化」への理解と対応に話を戻しますが、看護教育に携わる者として、労働の場で若い人を支える立場として、教員自身が「制度の意味」や「自分の働き方の特徴・限界」についてもしっかり理解しておく必要があると感じています。
淺野:大学教員の働き方に関しては、「専門業務型裁量労働制」という働き方の制度を活用することが法律上可能です。この制度は、業務の遂行時間や方法について、労働者自身に裁量がある(使用者が具体的な時間管理をしない)という特徴があります。深夜労働や休日労働については、通常の労働基準法の規制が適用されますが、日中の労働時間の管理は労働者に委ねられます。導入できる業務は限定されており、大学教員のほかには、たとえば、公認会計士、弁護士、一級建築士などが該当します。
ただし、高校教員などはこの制度を使えません。同じ「教員」でも対象か否かは労働基準法で明確に対象職種として定めがあるかどうかによって異なります。この制度の適用対象となる労働者像は、事業主と対等に交渉し、自律的に働き方を決定できる人が想定されていますが、実際には、時間外手当の割増賃金を払わなくて済むように「任せているだけ」といった形で濫用されている事例や、賃金を定額にとどめるためのからくりとして悪用されるケースもあります。そのため、制度の適正な運用には労使協定の締結や届け出のほか、制度導入にあたっては就業規則の整備も必要とされています。さらに2024年4月1日からは、制度の適用にあたっては対象労働者の同意が必須要件とされ、仮に同意しなかったとしても、そのことで不利益扱いをしてはならず、同意の撤回も可能となるなど、労働者保護の規定が強化されています。
大学教員の仕事は、他の先生との授業調整や研究活動のスケジュール調整があり、労働者が自由に時間配分を決められるかは議論があります。つまり、「裁量労働制」として適用していても、実態は厳密な意味での業務遂行についての時間配分等の労働時間の裁量を労働者に委ねているとは言い難い事例も多々あります。こうした場合にまで専門業務型裁量労働制を適用しようとすることは避けなければなりません。他方、専門業務型裁量労働制が使えない場合でも、フレックスタイム制のように一定の労働時間を確保しつつ、出勤・退勤時間を柔軟に調整できる働き方も活用可能です。フレックスタイム制の場合には、たとえば、通勤ラッシュを避けるために出勤時間をずらしたり、自分の生活リズムに合わせて働ける点にメリットがあります。
看護大学教員や教育関係者としては、こうした働き方の制度のメリットだけでなく限界や問題点も理解し、学生や若手看護師に正しく伝えることが重要です。制度の趣旨や労働者の権利、交渉力の問題、労使協定の重要性なども含めて、ワークルール教育のなかでしっかり扱うべきテーマといえます。
内山:私が知る範囲では、休職する人が増えてきているように思います。誰かが休むと、その仕事は別の誰かが担わなければならず、もともと決められた自分の仕事に加えて、人の仕事まで負担することになります。その結果、休職の連鎖が起きる場合もあります。こうした状況は、ワークルールとしてどのように理解し、どう対応すればよいのか難しい問題です。人が補充されることを希望したとしても、業務の内容によっては簡単にはできない場合も多いので、どのように考えたらよいのか……。
淺野:私の勤務先では、在外研究などで海外に行かれている方は何人かいます。その間は大学が非常勤講師をしっかり補充したり、休んでいる方が担当していた学内業務を別の方が分担したりしていて、特定の個人に過剰な負担がかかる感覚はあまりありません。そういう意味では、適切に人員が配置されていると言えるかもしれません。
休んだ方の業務をどこまで引き受けなければならないのかという問題は、まず契約内容を確認することが大切です。契約で業務内容や所定労働時間が明確に定められている場合、その範囲内での勤務が基本となります。これはデフォルト、つまり初期設定の状態です。もし契約の範囲を超えて業務を依頼されるのであれば、それは時間外労働となり、割増賃金が発生するものと考えるべきです。だから、契約外の業務を「当然やれ」と強制されることはあってはならず、きちんと話し合いをする必要がありますし、残業が生じるならば、それを可能とする仕組みの整備ができているのかを確認する必要があります。その際には36(サブロク)協定と呼ばれる労使協定の締結・届出がなされているのかを確認し、その範囲内で残業を命じる契約上の根拠が整っているかをチェックする必要があるのです。そして、業務命令が本当に必要なものかどうか、そして、もしやることになれば所定労働時間を超える分は賃金の支払いが必要となり、しかも、それが法律上の労働時間の上限(1日8時間、週40時間)を超える場合には割増賃金の対象になることを、明確に確認しておくべきだと思います。その対価が支払われないまま追加の業務を強いられるのは、違法である可能性が高いです。
内山:働くということの本質は、制度やルールに従うだけではなく、自らの専門性と誇りを守り育てていく営みなのだと、あらためて実感しました。そのなかでワークルールの知識が果たす役割の大きさを再認識しました。教員として、学生に知識と技術だけでなく「賢く働く力」をどう伝えていくか──これは今後も向き合い続けるべき課題であることを教えていただきました。本日はありがとうございました。
|
インタビューを終えて 淺野先生との対談では、「裁量労働制」や「前倒し残業」「同調圧力」など、現実の複雑さと法制度のギャップを丁寧に見つめ、どうすれば人間らしく働き続けられる職場をつくれるのか、その手がかりを共に探ることができたように思います。看護の現場における「働き方」とは、ただ規則や制度を守ることにとどまらず、1人ひとりが専門職としてのやりがいや健康、成長をどう両立させていくかという、きわめて実践的な問いだとあらためて感じました。そして、ワークルールとは、現場の課題を“わがこと”として理解し、働く人びとが自らを守り支え合うための道具でもあることを実感しました。 この対談が、看護の世界で学ぶ方々や現場で働くすべての人たちにとって、「働き方」を見直すきっかけになれば幸いです。 |