- 看護師
- 准看護師
- 精神看護学
- 教育方法
偏見を和らげ、学習意欲を喚起する 精神看護学における授業の工夫
第1回 北部看護学校の精神看護学
-
 動画
動画
- #精神看護
- #映画
- 2025/01/23 掲載
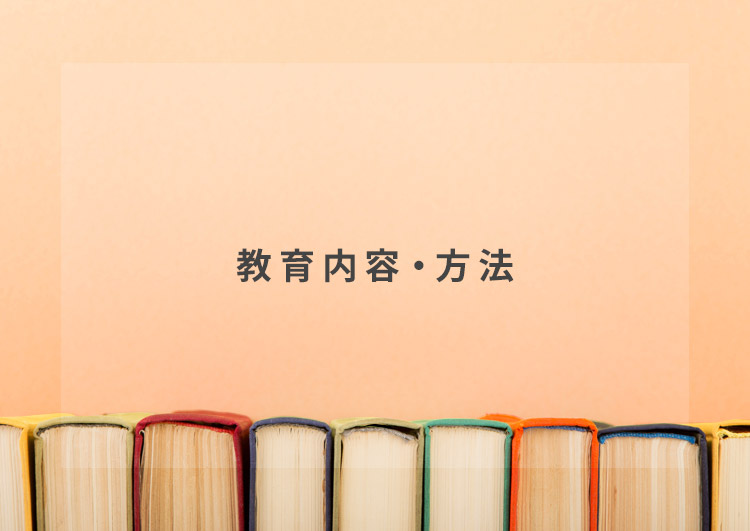
北部看護学校(以下、本校)の設置主体は北部地区医師会で、沖縄本島の北部地域である名護市で周囲は緑豊かで自然が多い地域に位置しています。3 年課程の学校で、定員は 1 学年 80 名、今年度(2024年度)で創立 32 年を迎えています。

北部看護学校
精神看護を学ぶ学生の偏見をどう乗り越え、理解を促すか
本校の学生は約 8 割が高校からの新卒者であり、社会人経験者 2 割のうちの多くが看護補助者・医療事務などの医療関係経験者ですが、ほとんどの学生がこれまでに精神疾患患者と関わった経験はありません。そのため、精神疾患に対する「社会的偏見」も加わり、精神看護学を学ぶ上での難しさにつながっていると思われます。
私は当初から、学生の持つ「偏見」は「未知・無知」の状況から産まれているものであり、看護基礎教育の中で「正しい知識の獲得と経験をする」ことでだいぶ和らぎ、かつ精神看護に対する理解と学習意欲を喚起するものと考え、科目内容と教授方法を工夫して構築・実践してきました。
もちろん、臨地実習において、精神疾患を患った患者と接する経験の中で達成できる課題ではありますが、その実習に出向く直前、あるいは実習前半あたりまでは、初めて接する患者を目の前にして学生の緊張と構えが強いこともあり、実習以前の学内の講義の中で「正しく理解」し、「接する経験」をすれば、実習での学びが効果的になると考えています。
今回「NEO」で、私が実践してきた精神看護学の授業の工夫と学生の感想を 3 回に分けて皆さまと共有したいと思います。授業づくりの参考の一助となれば幸いです。
|
第1回 北部看護学校の精神看護学 |
第 1 回では、本校の精神看護学の講義を連載の概説としてお示しします。
北部看護学校における精神看護学の講義の構築
ライフサイクルにおいて、身体的・精神的・社会的側面から総合的に理解を深め、人々の精神の健康の促進、疾病の予防、回復などへの援助を行うために必要な精神看護について学びます。本校では、4 単位 90 時間を以下のように構築しています。
精神看護学概論(1 単位 15 時間)
精神医療の歴史および精神保健における法制度の変遷をふまえ、社会環境の変化やライフサイクルにおける精神の健康と保健に関して学ぶ。
- 精神保健・看護の基本概念
- ライフルサイクルにおける心の発達と健康
- 患者―看護師関係の理解
- 危機介入とストレス理論
- リエゾン精神看護
- 精神医療の歴史と変遷 など
精神看護学方法論 1(1 単位 30 時間)
精神の症状・疾患と治療モデルの理解を通して看護実践の裏付けとなる理論的枠組みを学ぶ。
- 精神障害とその治療の理解
- 心理検査・精神療法
- 精神障害の理解
- 精神に障害のある人の生活を支えるシステム
- 病院における治療環境と看護の役割・機能 など
精神看護学方法論 2(1 単位 30 時間)
看護看護の基本を学び、精神疾患に関連する問題および保健医療福祉の視点から精神看護の方法を具体的に学ぶ。
- 精神看護の基本
- 主要症状別看護
- 疾患別看護
- 各治療時の看護
- 地域で生活するための支援 など
精神看護学方法論 3(1 単位 15 時間)
精神に障害のある人の事例をもとにした看護過程を展開し、総合的な看護の視点を養う。
***
今回、特に力を入れている精神看護学方法論 1 に掲げる「精神障害の理解」「精神に障害のある人の生活を支えるシステム」の学習で行っている 2 つの工夫について紹介したいと思います。
1 つは、疾患を学習する前に疾患の理解と患者の心理を理解する目的で、映画の鑑賞を取り入れています。これは、これから学ぶ精神疾患の理解と学習動機を高めることにもつなげる目的もあります。第 2 回でご紹介します。
もう 1 つは、ひと通りの疾患を学習した後に、当事者と直接対面して体験談の聴取や意見交換をすることで、患者の持つ苦悩・気持ちに寄り添うとともに、精神疾患患者は何も特別で異質な人ではなく、われわれと同じ「ひとりの人間であること」の理解を促しています。こちらは第 3 回でご紹介します。
 学校から望む名護の景色
学校から望む名護の景色

