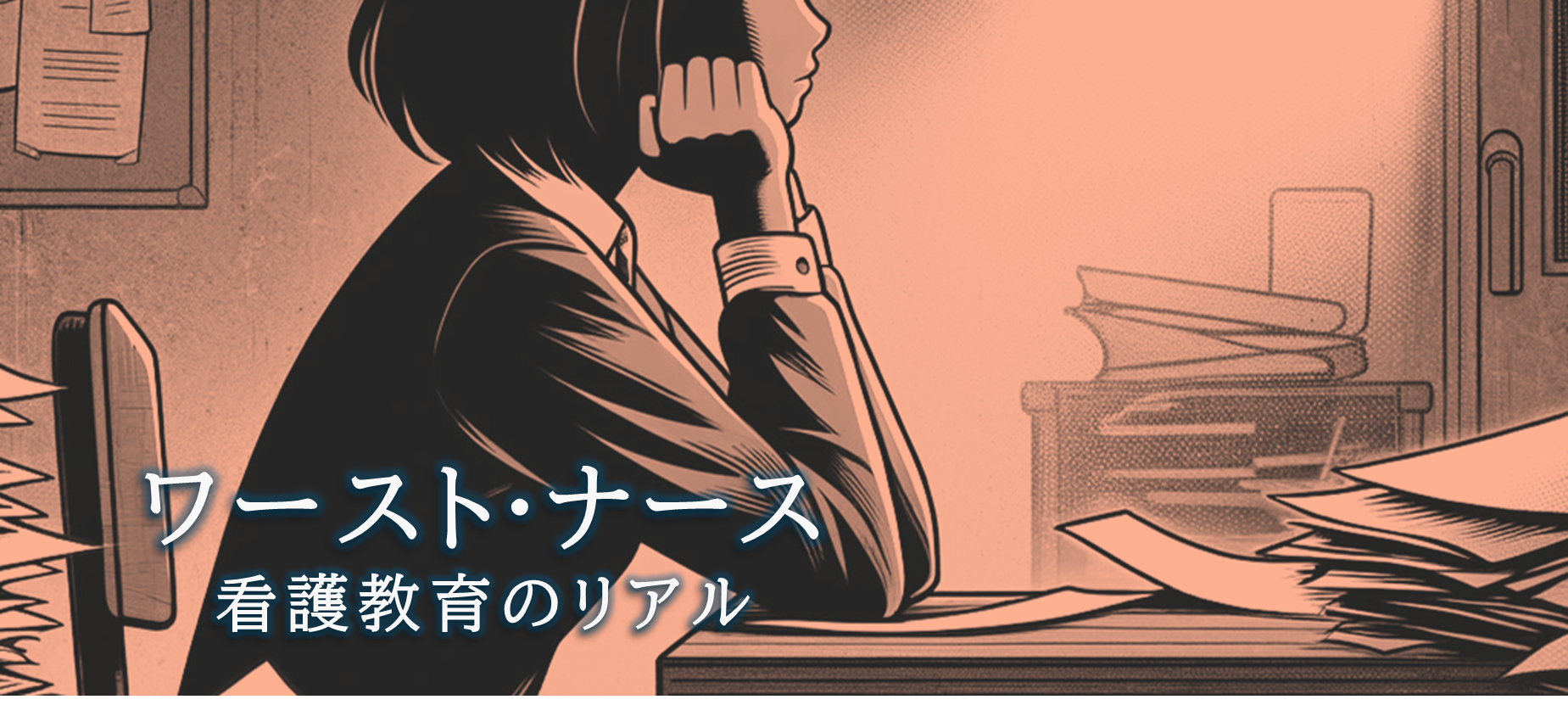- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 5年一貫
- 看護論
- 教育論
【小説】ワースト・ナース~看護教員のリアル~
第 5 話 意欲なき看護学生 (3)
- #看護教員
- #看護学生
- 2025/09/24 掲載

留年を選んだ山下さんは、1 年後の実習で合格するという道を選んだ。
しかしその目標を達成することはできず、結局、退学せざるを得なかった。
いち教員でしかない私には、学生や保護者の決定を否定することなどできない。
できることといえば、保護者に対して学生の状況をありのまま伝え、
学生自身が自分の気持ちをはっきり表明できるよう関わることくらいだ。
それでも、このような学生の指導にあたった際は、いつも「もっとできることがあったのではないか」という思いに駆られる。
看護という仕事に対し、興味や関心を持ってもらえるような関わり方ができたのではないか、と。
看護学実習は、患者さんとの関わりやケアに喜びややりがいを見出せた学生にとっては素晴らしい経験となる一方、
そうでない学生には苦痛以外のなにものでもなくなってしまう。
なぜなら看護を考えるための看護過程の展開は、一夜漬けの学習で理解できるようなものではないからだ。
目的や必要性を見出せないまま、目についた情報を羅列するだけでは、看護を考えることなどできない。
私は学生の学習進度に合わせ、「なぜ患者さんの情報を得る必要があるのか」という目的から伝えるようにしてきたが、
彼女の目には「実習に合格するために必要なもの」としか写っていなかった。
そこに「患者さん」という対象は存在せず、毎日テキストに書いてあった通りの症状を機械的に質問し、
記録するだけで終わってしまった。
いくら看護大学の学生として受け入れたとはいえ、看護に興味がもてず、
学習の姿勢もまったく見えない学生に対して、看護教員はどう向き合うべきなのだろう。
「わからない」のではなく、「勉強していない」「看護師を目指す気がない」に対して、
どこまで手を差し伸べるべきなのだろう。
なにより看護実習は、患者さんの協力があってこそ成り立っている。
病気や治療に苦しむ患者さんに、Aのような学生の受け持ちをお願いするたび、私は心苦しさを感じていた。
「この学生は、あなたを受け持たせていただくにあたって必要な知識が不足しています。看護への興味もなく、実習に行けばどうにかなるという気持ちで病院に来ています」
このような説明をして、快く学生を受け入れてくれる患者さんやご家族がいるだろうか。
もちろん、看護師になるために一生懸命学び、患者さんと誠実に向き合っている学生は大勢いる。
しかし、いくら看護の大学で厳格な入学試験を課したとしても、山下さんのような学生は一定数存在する。
「大学である以上、学生が主体的に学ぶことが前提だ」
「看護師資格を取得するために来たのだから、そのために学ぶのは当だろう」
というのは、至極もっともな意見だ。
しかし、「大学全入時代」と呼ばれ、全国に看護学部のある大学や専門学校が多数存在している現在、
看護師を目指すために入学してきた学生ばかりではないことを、私たち現場の教員は知っている。
なぜ、明らかに学習が不足している学生を実習に連れて行かなければならないのか。
そのような学生を患者さんにお願いせざるを得ない現実を、どう受け止めればよいのか。
そんな気持ちに襲われるとき、私はふと学生時代の自分を思い出す。
看護に特別な情熱があったわけでもなく、「安定した就職先」程度にしか考えていなかった、怠惰な学生だった自分を。
そして、真面目でも優秀でもなかった先輩、同期、後輩たちが、今では第一線で活躍しているということを。
自堕落な学生でしかなかった自分が、いまは看護教員として学生の前に立っている。
この構図には、どこか居心地の悪さがつきまとう。
しかしその一方で、私だからこそ伝えられることもあるのかもしれない、という気もしている。
実際、そのつもりでこの道を志したのだから。
この記事をご覧の方の中には、私と似た学生時代を過ごした人も一定数おられるだろう。
臨床に出てからはじめて看護という仕事にやりがいを見出し、一人前の看護師になった方が。
そうであるならば、いったい誰が、学生時代の実習のみで「向いていない」などと言い切れるだろう。
学生時代は不真面目のように見えた学生であっても、卒業後は一人前の看護師として活躍していることなど珍しくもない。
だからこそ、「今その時期」のみで学生を判断することはできないし、あってはならないことだと思っている。
しかしその一方で、看護という道に固執させることで別の可能性を閉ざし、
学生やその保護者を苦しめてしまう可能性もある——そのリスクもまた、見過ごせない。
だから私は思う。
私たち看護教員の真に大切な職務は、「学生を評価すること」ではなく、
「看護の魅力や責任を、誠実に伝えること」なのだと。
少なくとも「患者さんに対し、何の後ろめたさもなく協力をお願いできる」くらいには、
看護に対する心持や意識をもってもらえるように。